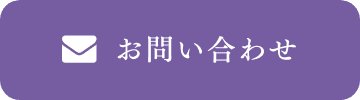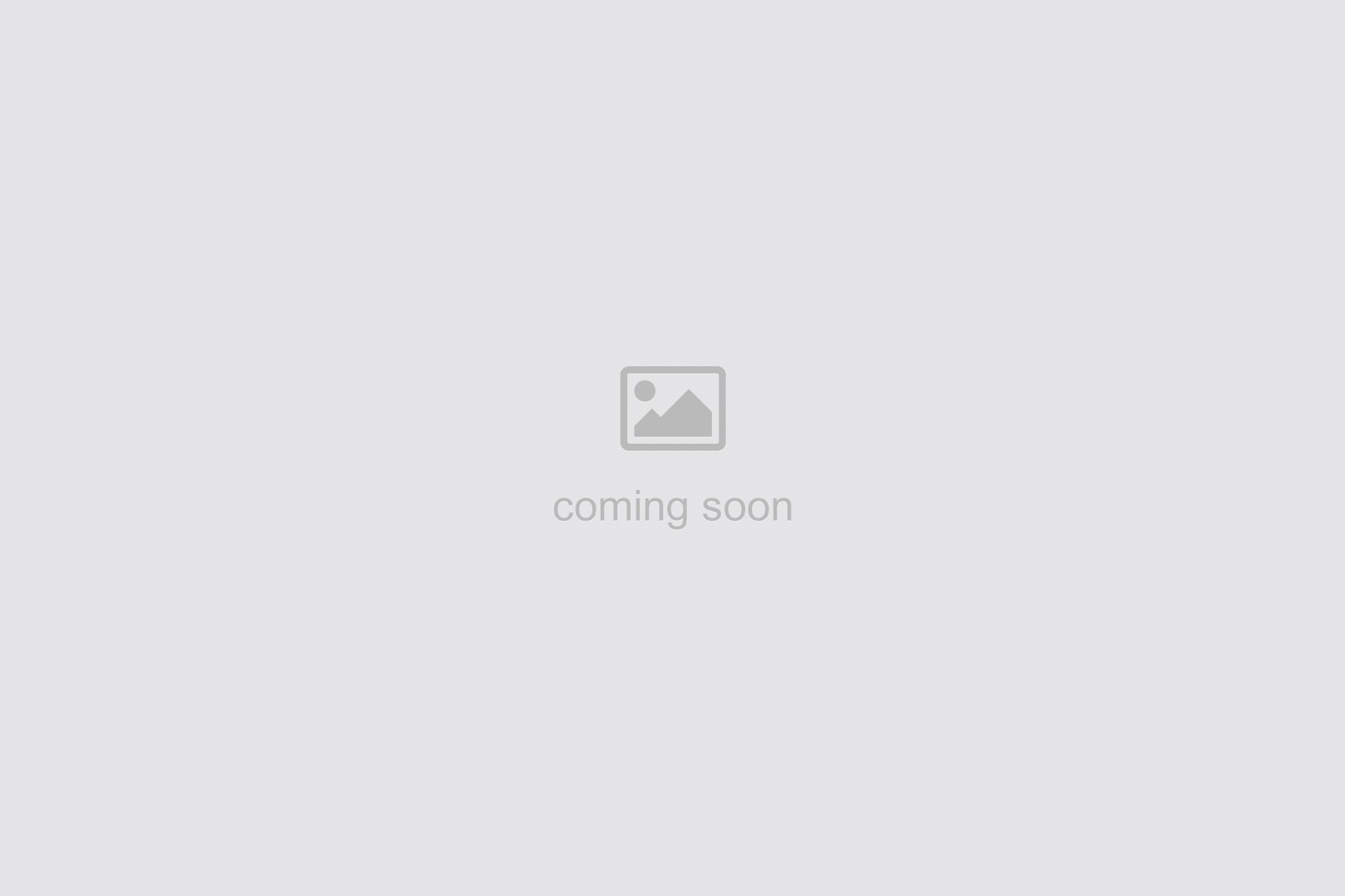心に残る名文

第5回 藤原道長「此の世をば」『小右記』(藤原実資)より

「心に残る名文」の第2回にて、古今和歌集から「月」にまつわる切ない素敵な和歌が1首紹介されています。(チェックされていない方はぜひバックナンバーもご覧ください!)
第5回では「月」は「月」でも全く観点の違う和歌を紹介したいと思います。
此の世をば我が世とぞ思ふ望月の かけたることも無しと思へば
(『詳説 日本史資料集』山川出版社)
《大意》満月の欠けたところがないように、この世は私の思い通りの世の中だ
おそらく、ほとんどの方は「国語」ではなく「社会」の授業で一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。平安時代、藤原摂関政治の全盛期を築いた藤原道長が詠んだとされる和歌です。
……すごい歌ですよね。社会の授業で初めてこの歌の存在を知りましたが、当時「なんて自信に満ち溢れた(傲慢な)人なんだ」と衝撃が走った記憶があります。
通称「望月の歌」とも呼ばれるこの和歌ですが、後世に残るきっかけとなったのは、藤原実資という人物が書いた日記『小右記』の一節に記されていたことでした。(ちなみに、道長本人も『御堂関白記』という日記を書いていたのですが、こちらにはこの和歌の内容までは記していないようです。)
道長が「望月の歌」を詠んだのは、三女の威子が後一条天皇の后となり、その宴が開かれた日でした。兄が次々と病に倒れたことにより突然巡ってきた摂政・関白の地位、ライバル伊周との政権争いに勝利、自分の娘を相次いで天皇に嫁がせることに成功、揺るぎない地位を確保……と、道長自身、また藤原氏摂関政治にとっても、まさに絶頂の時だったのです。どこも欠けていない満月を見ていたら、自分と重なって思わず喜びが口から出てしまった……というところでしょうか。
さて、上記で述べた通り『小右記』は藤原実資という人物によって書かれた日記です。当時の様子として、著者・実資は『ご機嫌な道長に「これから歌を詠むから返歌を考えてくれ」と事前に頼まれていたにも関わらず、実際に道長の望月の歌を聞くと「あまりにも歌が優美で返歌ができません」と返し、結局、望月の歌をみんなで復唱した』という出来事を日記に記しています。実資自身、政権のトップになれる立場ではなくとも、道長に意見を言うことができる地位ではありました。また、道長に一目を置きながらも、当時の政権に批判的な様子も見られます。そう考えると、この実資の返答は「謙遜」というよりは「皮肉」の意が込められているとも感じられます。あまりにも傲慢な歌に、実資は答えを返しながら「月はいつか欠けるものでしょう」と心の内で思っていたのかもしれませんね。
さらに、「日記」のため、少なからず実資の主観で記されているでしょう。一説では若いころから病気(糖尿病)に悩まされていたという話もある道長。『小右記』にも道長の病状について記しているため、実資も知っていたはずです。そして、症状がひどくなっていったのは、この和歌を詠んだ後からだそうです。また、揺るぎない地位を築けたのはただ運に恵まれていただけではなく、策略家の一面があったからでもあります。娘を天皇に嫁がせて天皇の親戚になっただけではなく、それを自ら存分に利用して、政治の実権を握っていったのです。
果たしてそんな人物がこんな短絡的な歌を詠むでしょうか?
歴史書から読み取れる道長像は「短気で豪胆」というのが一般的です。紫式部の「源氏物語」の主人公・光の君のモデルの一人とされているくらいなので、カリスマ性もあったのでしょう。トップに立つが故に不安を人には見せない人だったのかもしれません。しかし、そのような道長があえて自身を形が変化する「月」に例えたところから、表向きの自信の裏側にひっそりと「望月(満月)のままでいたい」という願いを込めていたのではないか? と、思わず考えてしまいます。
柴
第4回 いろは和歌【ろ】「櫓もおさで」『和泉式部集』より

櫓 もおさで風にまかするあま舟のいづれのかたによらんとすらん
(岩波書店『和泉式部歌集』)
作者の和泉式部は、恋多き和歌の名手として知られた女性ですが、この作品からはそのような華やかさよりも、自分の内面をじっと見つめるような陰が感じられます。
櫓も使わずに風にまかせて漂うあま舟は、いったいどこへ寄ろうとするのでしょう。
寄る辺なく漂う船に、自分自身を重ねているようです。
この和歌は、四十三首からなる歌群の中の一首。
歌群には、「身を觀ずれば岸の 額 に根を離れたる草、命を論ずれば 江 の 頭 に繫がざる舟」と読む、漢文の題がついています。
根が岸を離れた水辺の草や、入り江に繋がれていない船のように、この身も命も寄る辺なく不確かなもの――上の和歌とのつながりを感じます。
さらに、つながりをもう一つ。
一首だけではわかりませんので、歌群の初めの五首を並べました。
みる程は夢もたのまるはかなきはあるをあるとて 過 すなりけり
をしやへる人もあらなんたづねみん吉野の山の岩のかけみち
觀ずればむかしの罪をしるからになほ目のまへに袖はぬれけり
すみの江の松にとはばや世にふればかかる物おもふ折やありしと
例よりもうたてものこそ悲しけれわが世のはてになりやしぬらん
はかなくてけぶりとなりし人により雲ゐのくものむつまじきかな
(岩波書店『和泉式部歌集』)
一つ一つの和歌の冒頭の音だけを順に読んでみてください。
「み・を・かん・す・れ・は」となりますね。
「身を觀ずれば……」という、歌群の題の始めの部分と同じです。なんと、四十三首の冒頭の音をつなげると歌群の題になるのです。
どうしてこんなに大変なことを……? などと思ってしまいますが、四十三首の和歌を何度も何度も読んでいると、作者自身の思いを言葉の一つ一つにしっかり込めるためにどうしても必要な形式であり、儀式に近いような作業だったのかもしれないな、とも思うのです。
福井
第3回 国木田独歩『忘れえぬ人々』1898(明治31)年

国木田独歩は、とても流麗な文章を書く作家です。
高校の教科書で初めて読んだ『武蔵野』は、記憶に残る名文でした。その恩恵に浴して、『春の鳥』や『画の悲み』、『牛肉と馬鈴薯』などを読んで、独歩に少し近づいたかなと思ったのも遠い昔となりました。
独歩は37歳という若さで病没したため、作品は多くありませんが、きめ細かい情景描写が極めて上手な作家だと思います。特に、27歳のときに書かれた『忘れえぬ人々』は、いつ読んでも心に響くものがあります。
主人公の大津弁二郎は、作者と同年齢の無名の文学者です。ある日、多摩川沿いは溝口の旅人宿で、秋山という同年齢の無名画家に出会います。うら寂しい田舎の宿で話がはずみ、秋山は大津の書きかけの原稿『忘れ得ぬ人々』に妙に関心を示すので、大津は、眠れぬ夜の退屈まぎれに、原稿に書いてあるより詳しく鮮明に、それらの人々の話を秋山に語って聞かせるのでした。
その中の一つが、夕暮れの山道を、空車をつけた馬を引いて村に帰る若者の話です。
大津が弟と二人で、熊本から阿蘇を越えて大分まで横断したときのことです。日がとっぷりと暮れて、ようやくふもとの宮地の村に近づいたので、疲れた足を橋の欄干に休めながら、阿蘇のすさまじい噴煙の美しさに見とれていました。そして、一日の仕事を終えて、にぎわう村落の老若男女の声や、馬のいななきなどを聞くともなしに聞いていると、空車の音が虚空に響き渡って、しだいしだいに近づいてくるのに気がついたのです。
暫くすると朗々な澄んだ声で流して歩く馬子唄が空車の音につれて漸々と近づいて来た。僕は噴煙を眺めたままで耳を傾けて、此の声の近づくのを待つともなしに待っていた。
人影が見えたと思うと「宮地やよいところじゃ阿蘇山ふもと」という俗謡を長く引いて丁度僕等の立っている橋の少し手前まで流して来た其の俗謡の意と悲壮な声とが甚麼に僕の情を動かしたろう。二十四五かと思われる屈強な壮漢が手綱を牽いて僕等の方を見向きもしないで通ってゆくのを僕はじっと睇視めていた。夕月の光を背にしていたから其の横顔も明毫とは知れなかったが其の逞しげな体躯の黒い輪廓が今も僕の目の底に残っている。
僕は壮漢の後ろ影をじっと見送って、そして阿蘇の噴煙を見あげた。「忘れ得ぬ人々」の一人は則ち此の壮漢である。
(『底本 国木田独歩全集第二巻』学習研究社 ルビは引用者による)
この壮観さは、どうでしょう。
明るく澄んだよく通る声、荷物の乗っていない車の軽快な音、そして、馬のひづめの悠長な響き、それらがだんだん近づいてくると、流して歩くその声の主は屈強な壮漢であることがわかりました。
その姿と凛々しいまでに澄んだ声から、壮漢が如何に日々の生活にひるまず、たくましく生きているかということが伝わってきて、主人公の情を強く動かしたわけです。
阿蘇山のふもとのたくましい壮漢の黒い輪郭が、一枚の絵のように「今も僕の目の底に残っている」のは、単に美しい風景の中に融け込んだだけの壮漢ではなく、悲壮な声で歌を流して歩きながら颯爽としているその姿に、身が引き締まるような感動を覚えたからにほかなりません。
阿蘇山とそこから上る噴煙の雄大さに見とれているうちに、歩き通して疲れている主人公の心持ちとがあいまって、この壮漢にすっかり魅入られてしまった様子が、如実に語られていてすばらしいと思います。
すなわち、これが、私の「忘れ得ぬ名場面」の一つです。
清し女
(肖像写真は国立国会図書館蔵)
第2回 いろは和歌【い】「いま来むと」『古今和歌集』より

第1回 夏目漱石『硝子戸の中』1915(大正4)年

『硝子戸の中』は自伝ではありませんが、自分の過去と現在を入り交えて書いためずらしいエッセイです。風邪をひいて書斎に閉じこもり、部屋の中から硝子戸を通して、外を眺めつつ書き綴ったものというところから、このタイトルがついたようです。
今回紹介するのは、若いころに住んでいた馬場下界隈のことを記した箇所です。馬場下というのは、高田の馬場の下という意味で、当時東京では「辺鄙な隅の方にあった」ところだそうです。
当時私の家からまず町らしい町へ出ようとするには、どうしても人家のない茶畠とか、竹藪とかまたは長い田圃路とかを通り抜けなければならなかった。買物らしい買物は大抵神楽坂(かぐらざか)まで出る例になっていたので、そうした必要に馴らされた私に、さした苦痛のあるはずもなかったが、それでも矢来(やらい)の坂を上(あが)って酒井様の火の見櫓(やぐら)を通り越して寺町へ出ようという、あの五、六町の一筋道などになると、昼でも陰森(いんしん)として、大空が曇ったように始終薄暗かった。
また、半鐘の記念のための句は、正岡子規がまだ生きていたときに作ったものだといいます。馬場下界隈を思い出しながら、親友であった子規にも思いを馳せているところは、この一節の結びに花を添えているように思います。
清し女