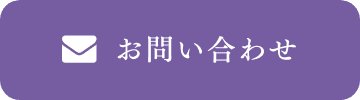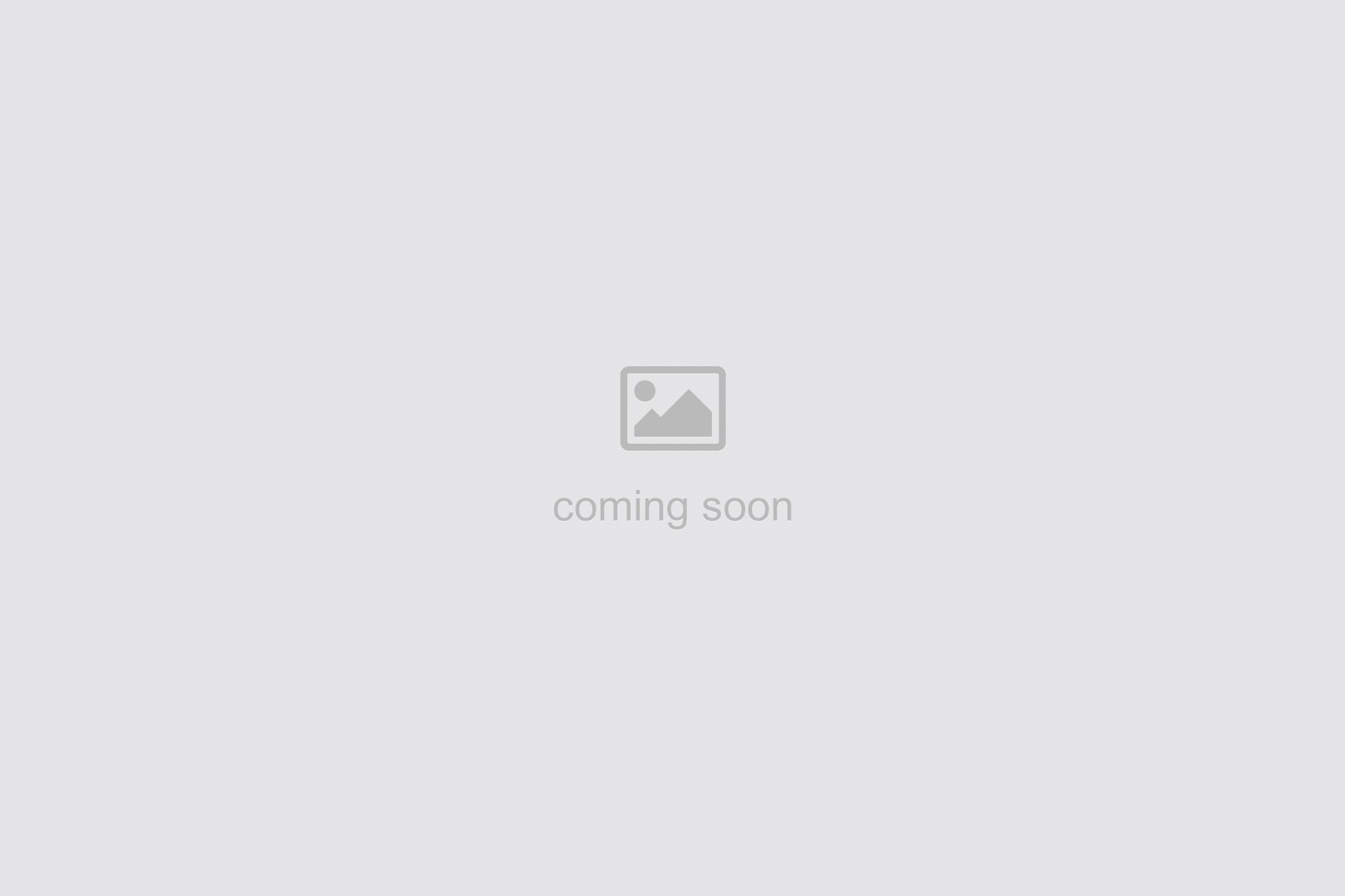心に残る名文

小説や随筆などを読んでいると、
「これは名文中の名文だな」と思う場面に出会うことがあります。
ありありと情景が目に浮かび、懐かしいものを見るような気持ちになったり、
その世界に引き込まれて、時を忘れたりしてしまいます。
想像力をたくましくし、自在に情景を思い浮かべるのは楽しいものです。
写実的な表現に一幅の美しい絵を見ているような気持ちになったり、
滋味のある文体にしみじみとしたり、
ユーモアに富んだ言葉遣いに思わずほくそ笑んだり、
――そういう文章に出会えることは、本当に幸せなことです。
そのような文章を「心に残る名文」と題して、
ここに紹介していきます。
第25回 坂口安吾『風博士』
2019-05-13

初めて記事を書きます。挨拶として、坂口安吾『風博士』の最後の2文を紹介します。大学の授業で扱われたそれは私を驚愕させ、授業への集中を奪ってしまいました。その衝撃を伝えるため、まずは『風博士』のあらすじの紹介から。
この物語の語り手は風博士と呼ばれる先生の弟子である「僕」です。「僕」は、風博士が自殺し、その件について警察にあらぬ疑いをかけられていると言います。しかもその自殺には蛸博士という人物が深く関わっているらしく、とにかく風博士の遺書を見て欲しいと読者に語りかけます。それはまあ図々しい語り口で。
風博士の遺書には、ただひたすら蛸博士への悪口がしたためられていました。蛸博士は髪の毛が薄いとか、自分(風博士)が踏んづけて転んだバナナの皮は蛸博士が置いたに違いないとか、自分の妻を奪ったのは蛸博士だとか、自分の方が彼よりかっこいいだとか。そして、風博士は蛸博士を困らせようと鬘を盗んだようなのです。しかし、蛸博士は別の鬘をかぶって現れ、それにショックを受けた風博士は自殺を決意したとのことでした。
遺書が終わり、弟子は風博士の決定的な最期について読者に教えてくれます(相変わらずの図々しさで)。博士は書斎で風になって消えたと言うのです。だからもう姿はないと。
語り手の「僕」、風博士、蛸博士等が登場しますが、私たちは誰のことも信用できません。「ずっと何を言っているんだ」という状況です。バナナの皮で人は転ぶのでしょうか。そもそも風博士は人間なのでしょうか。何も分かりません。私たちが分かるのは「僕」も風博士も必死であること、くらいです。
そんなこんなで、最後の2文にたどり着きます。たどり着いてしまうのです。弟子である「僕」が風博士の死について、最後に一つ言い残します。
それでは僕は、さらに動かすべからざる科学的根拠を附け加えよう。この日、かの憎むべき蛸博士は、恰もこの同じ瞬間に於て、インフルエンザに犯されたのである。
「坂口安吾全集1」ちくま文庫
なんと「風」と「風邪」をかけた洒落でこの物語が締めくくられてしまいました。しかし騙されてはいけません。風博士が死んだ日に、蛸博士がインフルエンザになったことは何も「科学的」ではないのです。結局誰も信用できないまま、終わったようで何も終わっていないのです。騙されるところでした。突風で知らないところに連れていかれたようなこの読後感を私は忘れることができません。
安吾はファルス(笑劇)を愛していました。きっと考えてはいけないのです。風博士が何の比喩であるか、この物語は何なのか、考え始めたらそれこそ安吾に笑われる気がします。
小獺
第24回 いろは和歌【ぬ】 大伴百代「ぬばたまの」『万葉集』より
2019-04-08

新元号が「令和」と発表されましたね。出典は『万葉集』だそうです。
いろは和歌シリーズ、今回はその『万葉集』から、「ぬ」で始まる一首を紹介します。
大宰大監大伴宿禰百代の梅の歌一首
ぬばたまのその夜の梅をた忘れて折らず来にけり思ひしものを
(新編日本古典文学全集6 万葉集』小学館)
あの夜に見た梅を、うっかり忘れて折らずに来てしまいました。(この梅をと)思っていたのに。
作者である大伴百代は、天平(729〜749年)の頃に大宰府の役人だったといわれています。
「ぬばたま(射干玉)」はヒオウギという草の実のことですが、この実が真っ黒であることから、「ぬばたまの」という「黒」「夜」などにかかる枕詞として用いられるようになりました。
この歌は、『万葉集』巻第三に「譬喩歌」としてまとめられた中の一首。恋心を抱いていた相手を、梅にたとえているわけです。歌を詠む場にいた美しい女性を、戯れに梅にたとえたのだともいわれています。
大伴百代の歌は、その序が新元号の典拠となった「梅花の歌三十二首并せて序」(巻第五)にも含まれています。
そちらでは梅をどんなふうに詠んでいるのでしょう。ぜひ『万葉集』を手に取って探してみてください。
福井
第23回 いろは和歌【り】 良寛・貞心尼「霊山の」『蓮の露』より
2018-06-27

いろは和歌シリーズ、今回は「り」で始まる和歌を紹介します。
いざさらば立かへらむといふに
霊 山 の 釈 迦 のみ前に契りてしことな忘れそ世はへだつとも
御かへし
霊山の釈迦のみ前にちぎりてしことは忘れじ世は 隔 つとも
(「 蓮 の露」より『校注良 寛 全歌集』春秋社)
それでは帰りましょう、と言うので
霊山の釈迦の御前で約束したことを忘れないでください、世を隔てたとしても
お返し
霊山の釈迦の御前で約束したことは忘れません、世を隔てたとしても
一首目は良寛の、返歌は 貞 心 尼 の作です。
“良寛さま”のお話を聞いたことのある方は多いのではないでしょうか。「この里に手まりつきつつ子供らと遊ぶ春日は暮れずともよし」(『校註良寛歌集』岩波書店)という有名な和歌は、子どもたちと遊ぶのが好きだった良寛の人柄を表しています。
貞心尼は30歳のとき、初めて良寛の住まいを訪れたといわれています。良寛はそのとき70歳でした。二人の親交は、良寛が74歳で没するまで続きました。
貞心尼が編んだ歌集『蓮の露』には、良寛と貞心尼の歌のやりとりが多く収録されています。
「霊山」はインドにある 霊 鷲 山 という聖なる山で、そこで釈迦が仏教の教えを説き、集まった人々はその教えを世に広めることを約束したという逸話があります。
また、この良寛の和歌は、 飛鳥 時代の僧侶である 行 基 の「霊山の釈迦のみ前に契りてし真如くちせず逢ひ見つるかな」(「拾遺集」より 『校注 良寛全歌集』春秋社)という和歌を念頭に読まれたと考えられます。霊山の釈迦の御前での約束がやぶられることなく、また会うことができたなあ、という内容です。
「それでは帰りましょう」と言ったのは、良寛のもとを訪れていた貞心尼。
「世」は前世・現世・来世の三世を意味しています。仏の教えを伝え、次の世で再び会いましょうという前世での約束を、忘れないでください、忘れません、というやりとりです。
しばしの別れを惜しむ場面で交わされたこの唱和には、同じ時間を現実に共有した者どうしにだけ通う空気が漂います。互いに信頼し合い高め合う交わりの得難さが思われます。
福井
第22回 勝海舟『氷川清話』「西郷と江戸開城談判」
2018-06-06

今年2018年は明治維新から150年。
NHKの大河ドラマでは、「西郷どん」こと、西郷隆盛が主人公ですね。
私は、2010年の「龍馬伝」を最後に、大河ドラマを見なくなってしまったので、今年の「西郷どん」が、どんな活躍ぶりを見せているのかわかりませんが、西郷隆盛というと、なぜか江戸無血開城を連想します。
これまた大河ドラマで申し訳ありませんが、遠い昔、私が高校生だったころ、「勝海舟」を放映していました。そのドラマで初めて幕末動乱のすさまじさを知り、勝海舟をはじめとする多くの人物の名前を覚えた記憶があります。
その中で、勝海舟と西郷隆盛が、たった二人で江戸開城談判をおこなったということが非常に印象に残ったものでした。
『氷川清話』は、海舟が晩年に語った人物評や時局批判の数々を盛り込んだもので、その語り口調は豪快で人間臭く、海舟の懐の広さや人物の大きさを感じさせてくれる、魅力的で痛快な一冊です。
怖いもの知らずで、辛辣な批判が多く、めったに人を褒めることをしない中で、「おれは、今までに天下で恐ろしいものを二人見た。それは、横井小楠と西郷隆盛だ」と、手放しで恐れをなしているのですから、西郷隆盛という人は、やはりどでかい人物だったのでしょうね。横井小楠は、肥後出身の儒学者です。
この江戸城を明け渡す談判は、1868年3月13日と14日に行われたもので、幕府側の要人であった海舟が、官軍側の西郷隆盛を、どのように見ていたかということがよくわかります。
西郷なんぞは、どの位ふとつ腹の人だったかわからないよ。手紙一本で、芝、田町の薩摩屋敷まで、のそのそ談判にやってくるとは、なかなか今の人では出来ない事だ。
あの時の談判は、実に骨だったヨ。官軍に西郷が居なければ、談はとても纒まらなかっただろうヨ。その時分の形勢といへば、品川からは西郷などが来る、板橋からは伊地知などが来る。また江戸の市中では、今にも官軍が乗込むといって大騒ぎサ。しかし、おれはほかの官軍には頓着せず、ただ西郷一人を眼においた。
(中略)
当日おれは、羽織袴で馬に騎って、従者を一人つれたばかりで、薩摩屋敷へ出掛けた。まづ一室へ案内せられて、しばらく待って居ると、西郷は庭の方から、古洋服に薩摩風の引つ切り下駄をはいて、例の熊次郎といふ忠僕を従へ、平気な顔で出て来て、これは実に遅刻しまして失礼、と挨拶しながら座敷に通った。その様子は、少しも一大事を前に控へたものとは思はれなかった。
さて、いよいよ談判になると、西郷は、おれのいふ事を一々信用してくれ、その間一点の疑念も挟まなかった。「いろいろむつかしい議論もありませうが、私が一身にかけて御引受けします」西郷のこの一言で、江戸百万の生霊も、その生命と財産とを保つことが出来、また徳川氏もその滅亡を免れたのだ。もしこれが他人であったら、いや貴様のいふ事は、自家撞着だとか、言行不一致だとか、沢山の兇徒があの通り処々に屯集して居るのに、恭順の実はどこにあるかとか、いろいろ喧しく責め立てるに違ひない。万一さうなると、談判は忽ち破裂だ。しかし西郷はそんな野暮はいはない。その大局を達観して、しかも果断に富んで居たには、おれも感心した。
この時の談判がまだ始まらない前から、桐野などという豪傑連中が、大勢で次の間へ来て、ひそかに様子を覗つて居る。薩摩屋敷の近傍へは、官軍の兵隊がひしひしと詰めかけて居る。その有様は実に殺気陰々として、物凄い程だった。しかるに西郷は泰然として、あたりの光景も眼に入らないもののやうに、談判を仕終へてから、おれを門の外まで見送った。
(中略)
この時、おれがことに感心したのは、西郷がおれに対して、幕府の重臣たるだけの敬礼を失はず、談判の時にも、始終座を正して手を膝の上に載せ、少しも戦勝の威光でもって、敗軍の将を軽蔑するといふやうな風が見えなかつた事だ。
(『氷川清話』講談社学術文庫)
ここに至るまでの道筋には、幕府側、官軍側それぞれ多くの策略や駆け引きが張り巡らされていたことと思います。しかし、円満に収まった最たる要因は、何といっても最後の大一番! 勝負をかけて取引に出てきた二人の役者が、超一流だったということなのでしょう。
江戸が戦火にまみれず、一滴の血も流れずに、一件落着したのですから。
清し女
(肖像写真は国立国会図書館蔵)
第21回 いろは和歌【ち】 読人知らず「散りぬとも」『古今和歌集』より
2018-02-15

いろは和歌シリーズ、今回は「ち」で始まる和歌を紹介します。
題しらず
読人しらず
散りぬとも香をだにのこせ梅の花恋しきときの思ひいでにせむ
(『新編日本古典文学全集11 古今和歌集』小学館)
花が散ってしまっても、せめて香りは残しておいてください、梅の花よ。
恋しいときの思い出のよすがとしましょう。
散る花を惜しむ思いが、素直に表現されていると感じます。
恋しき、の対象は、梅の花であり、人でもあるでしょう。
毎年、近所の公園に梅が咲きます。
少し気温の上がった休日に期待をこめて足を運ぶと、赤やピンクや白の小さな花が咲き始めており、お花見に来ている人もちらほら見えました。
少し離れたベンチで、ジャージ姿の女子大生が一人ぼんやり花を見ています。
別のベンチには老夫婦が並んで座り、「いい香りねえ」「いや全然香らんなあ」「あらあらおかしいわねえ」「なあ」と、笑いながらおしゃべりしています。
小さな男の子を2人連れた若い夫婦が、かわりばんこに記念写真を撮っています。子どもたちは梅よりも、拾った木の実に夢中です。
くたびれたダウンジャケットを着てビールの缶を持ったおじいさんが梅の木に近づいて、ラジオ体操の要領で深呼吸、その香りを胸に吸い込んでいます。
彼らがみんな立ち去った後、私もおじいさんの真似をしました。去年も一昨年もかいだ、春の香りです。
この歌の作者が思い出したいと願ったのは、どんな梅の花、どんな相手だったのでしょう。
名もわからない読み人に、聞いてみたい気がします。
福井