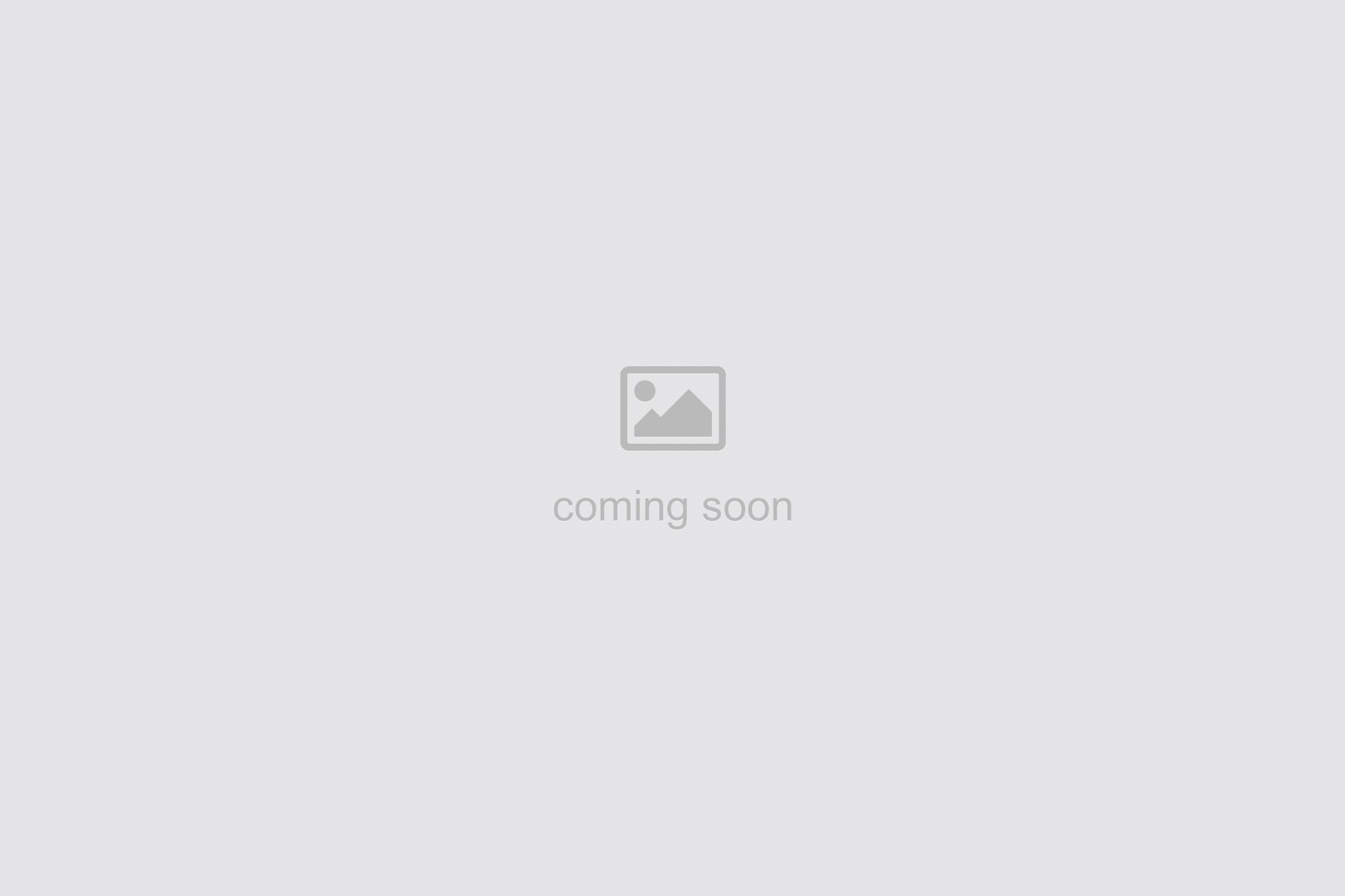心に残る名文

小説や随筆などを読んでいると、
「これは名文中の名文だな」と思う場面に出会うことがあります。
ありありと情景が目に浮かび、懐かしいものを見るような気持ちになったり、
その世界に引き込まれて、時を忘れたりしてしまいます。
想像力をたくましくし、自在に情景を思い浮かべるのは楽しいものです。
写実的な表現に一幅の美しい絵を見ているような気持ちになったり、
滋味のある文体にしみじみとしたり、
ユーモアに富んだ言葉遣いに思わずほくそ笑んだり、
――そういう文章に出会えることは、本当に幸せなことです。
そのような文章を「心に残る名文」と題して、
ここに紹介していきます。
第15回 寺田寅彦「天災は忘れられた頃に来る」
2017-03-30

平成23(2011)年3月11日、東日本大震災が発生しました。
千年に一度あるかないかの大震災と津波であったことを知った驚きと、東北地方の被害の甚大さにただただ言葉を失うばかりでした。
「大きな地震は、思い出したように、忘れた頃にやってくるのだ。『天災は忘れられた頃に来る』と言われているのだから、備えが大切だ」と、子どもの頃によく言われたものです。にもかかわらず、未だに備えも心構えも満足にできていないのが現状です。
この『天災は忘れられた頃に来る』という言葉は、物理学者であり随筆家でもある寺田寅彦(明治11(1878)年~昭和10(1935)年)が、弟子たちに常々言っていた言葉だと言われています。
ここであらためて、地震についての名文を確認し、気持ちを引き締めたいと思います。
昭和八年三月三日の早朝に、東北日本の太平洋岸に津浪が襲来して、沿岸の小都市村落を片端から薙ぎ倒し洗い流し、そうして多数の人命と多額の財物を奪い去った。明治二十九年六月十五日の同地方に起こったいわゆる「三陸大津浪」とほぼ同様な自然現象が、約満三十七年後の今日再び繰り返されたのである。
同じような現象は、歴史に残っているだけでも、過去において何遍となく繰り返されている。歴史に記録されていないものがおそらくそれ以上に多数にあったであろうと思われる。現在の地震学上から判断される限り、同じ事は未来においても何度となく繰り返されるであろうということである。
こんなに度々繰り返される自然現象ならば、当該地方の住民は、とうの昔に何かしら相当な対策を考えてこれに備え、災害を未然に防ぐことが出来ていてもよさそうに思われる。これは、この際誰しもそう思うことであろうが、それが実際はなかなかそうならないというのがこの人間界の人間的自然現象であるように見える。
(『寺田寅彦全集 第七巻』「津浪と人間」岩波書店)
※昭和8(1933)年3月3日、昭和三陸地震。
※明治29(1896)年6月15日、明治三陸地震。
天災は、記憶の新たなうちにやって来るのではなく、忘れられた頃に来るのだから、人間は過去の記録を忘れないように努力するよりほかはないと、寺田は言っています。また、文明が進むほど天災による損害の程度も累進する傾向にあるとも言っています。日本のように地震の絶えない国においては、文明の進化と同時に、耐震の技術も進化していかなければならないということなのでしょうが、現実には非常に難しいことなのでしょうね。
個人においては、さらにできることは限られています。せめて、慌てない、落ち着いて行動する、その気持ちを忘れないようにしたいと思います。
寺田寅彦は、東京帝国大物理大学実験物理学科を首席で卒業。その後大学院を経て物理学者になり、東京帝国大学地震研究所にも所属し、大正12(1923)年の関東大震災の調査にもあたっています。
そういう傍ら文筆活動も盛んに行い、数多くの随筆を残していることでも著名です。熊本第五高等学校で、夏目漱石に英語と俳句を習い、漱石の晩年まで親交が続きました。また、『吾輩は猫である』の水島寒月や『三四郎』の野々宮宗八のモデルとされているので、今後読む機会がありましたら、寺田寅彦を意識しながら読んでみるのも一興かと思います。
清すがし女め
第14回 島崎藤村「藤村随筆集」
2017-03-13

島崎藤村の随筆集の中に、音読について書かれた名文があります。
音読は、黙読より脳を刺激するので、脳トレになるらしいくらいに思っていました。しかし、音読や朗読をすることは、もっと奥が深いのだということを、教えてくれています。
寒鯥、鮟鱇、寒比目魚なぞをかつぎながら、毎日大森の方から来てわたしの家の前に荷をおろす年若な肴屋がある。冬の魚を売って行く。その後には何かしら威勢のいい、勇みなものが残る。こうした肴屋の声にかぎらず、いろいろな物売の声には、機械を通じて伝わって来る響にないものがある。町を呼んで通り過ぎる花屋の声のすずしさ、寒紅売のやさしさ、竿竹売のおもしろさ。あたりの空気をやわらげたり引き立てたりするものは、どうしても陰影の多い人の声にかぎるようだ。
ずっと以前にはわたしたちもよく声を出したものだ。少年時代に四書五経の素読から始めたわたしなぞは、声を出して読書することを楽しみに思ったばかりでなく、それを聴くことをも楽しみに思った。わたしたちの出す声は随分無茶で書生流儀のものではあったが、いくら叫んでも叫び足りなかったように、わたしたちの胸から迸り出るものが、いろいろな試みともなったのである。
どうも、この節は声を出すということが、どの方面にも少なくなったような気がする。どっちを向いて見ても、鳴りを潜めて、沈まり返っているような気がする。物をいえば口唇が寒いのか。吹き狂う世紀のつめたい風がこんなに人を沈黙させるのか。
書物に対してすら、今の私たちは音読の習慣を失うようになった。黙読、黙読だ。これは自分らのような年頃のものばかりでないと見えて、町を歩き廻ってもめったに若々しい読書の声をきかない。
「寝物語」1936(昭和11)年
すぐれた人の書いた好い文章は、それを黙読翫味するばかりでなく、時には心ゆくばかり声をあげて読んで見たい。われわれはあまりに黙読に慣れすぎた。文章を音読することは、愛なくては叶わぬことだ。
「初学者のために」1922(大正11)年
(『藤村随筆集』岩波文庫)
「愛なくては叶わぬことだ」と言い切るところは、すごいと思います。愛情を込めて読むとか、無心になって読むとか、そういうことでしょうか。難しい一文です。
最近、小学校の国語の授業で音読する様子を久しぶりに参観し、真剣な子どもの声とは張りがあっていいものだなと、しみじみ思いました。
また、ある中学校の先生の実践報告に、古典をもっと好きになってほしいということから、「平家物語」屋島の合戦を音読教材にしたということが書かれています。役割を決めて各パートに分かれ、台詞を暗唱して群読するのだそうです。最終的には、130人ほどの生徒が文化祭で、学年群読「平家物語」を発表するというのですから、その並々ならぬ指導もさることながら、生徒たちの根気と気力には目を見張るものがあります。きっとこの生徒たちは、音読の楽しさを体で覚えたことでしょうね。
2001年に発売された齋藤孝先生の『声に出して読みたい日本語』(草思社)がベストセラーになってから、17年になります。仕事に必要で続編併せて4冊購入し、座右の書のようになっていますが、そこには、「いま、暗誦文化は絶滅の危機に瀕している。かつては、暗誦文化は隆盛を誇っていた」と、書かれてあります。藤村と全く同じことを嘆いていることに、とても興味をもちました。
齋藤先生は、「歴史のなかで吟味され生き抜いてきた名文、名文句」を朗誦することによって、「その文章やセリフをつくった人の身体のリズムやテンポを、私たちは自分の身体で味わうことができる」、そしてまた、「世代や時代を超えた身体と身体とのあいだの文化の伝承が、こうした暗誦・朗誦を通しておこなわれる」と、言っています。
文豪藤村から、また、現代の大学教授から、声を出して名文を読むことの大切さを教えられた気がします。
清し女
(肖像写真は国立国会図書館蔵)
第12回 いろは和歌【ほ】 伏見院「星清き」『玉葉和歌集』より
2017-02-27

いろは和歌シリーズ、今回は「ほ」で始まる和歌を紹介します。
冬御歌の中に、雪を 院御製
星清き夜半の薄雪空晴れて吹きとほす風を梢にぞ聞く
(小学館『新編日本古典文学全集49 中世和歌集』)
星の清らかな夜半、薄雪が降った空はすぐ晴れて、木々の間を吹き通す風を梢に聞くことだ
「院御製」とありますが、作者は伏見院。生没年は文永二(1265)年~文保元(1317)年、第92代の天皇です。
このころは、天皇家が持明院統と大覚寺統という二つの系統に分かれていた時代(伏見院は持明院統)。鎌倉幕府との関係も複雑になり、武家と天皇家が入りまじった権力争いが繰り広げられていました。
そんな中、和歌の世界にもいくつかの流派が生まれていました。その中の一つに「京極派」という流派があり、伏見天皇は京極派の代表的な歌人でした。
京極派の和歌の特色として、自然の情景を正確に描き出そうとする叙景歌の存在が挙げられます。
今回紹介する和歌はどうでしょう。
冬のきりりと冷たい夜半の空気の中、空には星が清らかに瞬いている。雪は重たく積もるほどではなくさらりと降って、木々の間を吹き抜けてくる冷たい風が梢を揺らしている。清浄で鮮やかな情景が浮かびます。感傷的な雰囲気はなく、緊張感がある印象を受けます。
まだまだ寒い今日このごろ、春を待ち遠しく思いながらも、この和歌がもつきりっとした空気に触れると、冬が去ってゆくのが少し名残惜しいような気持ちになります。
福井
第11回 いろは和歌【に】 額田王「熟田津に」『万葉集』より
2017-02-07

いろは和歌シリーズ、今回は「に」で始まる和歌を紹介します。
熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな
(『新編日本古典文学全集6 萬葉集①』小学館)
熟田津で船出をしようとして月の出を待っていると、潮も満ちてきた。さあ、今こそ漕ぎ出そう。
万葉を代表する歌人、額田王の作品です。額田王の和歌は教科書などでよく取り上げられているので、聞いたことのある人が多いのではないでしょうか。
斉明七(661)年正月、中大兄皇子(後の天智天皇)の軍が、唐・新羅の連合軍と戦う百済を援護するために、飛鳥から北九州へ向かいました。この歌は、その途中で伊予(愛媛県)の熟田津という土地に立ち寄ったときに詠まれたと考えられています。
そろって船出を待つ大勢の軍。月が出て潮が満ち、いざ出航という場面です。声に出して読んでみると、歌の言葉に込められた戦勝への祈り、いざ進まんという力強い意志を感じます。
天皇に仕え、神事に携わり、職業的な歌人でもあったといわれる額田王。この和歌は、斉明天皇の歌として額田王が代作したものだという説もあります。
ところで、私が初めてこの和歌に触れたのは、『万葉集』でも教科書でもなく、井上靖の小説『額田女王』の一場面でのことでした。額田王は中大兄皇子と大海人皇子(天武天皇)の兄弟二人から愛されたといわれています。小説では、神に仕える者として、女性として、さまざまな思いを込めて歌を詠む額田王の姿が非常に魅力的に描かれています。「熟田津に……」の和歌が詠まれる場面も印象的。こちらもぜひ読んでみてください。
福井