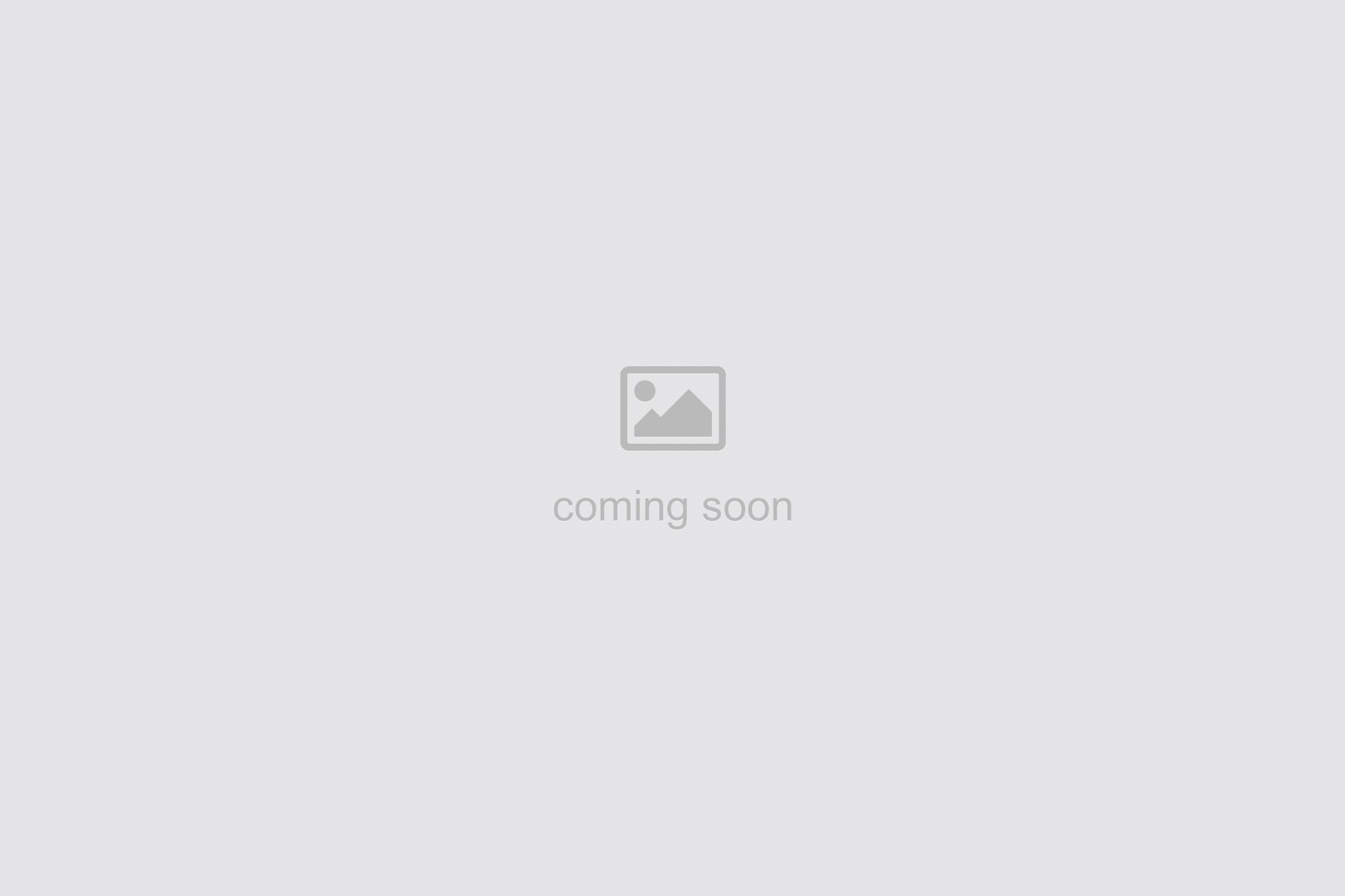心に残る名文

小説や随筆などを読んでいると、
「これは名文中の名文だな」と思う場面に出会うことがあります。
ありありと情景が目に浮かび、懐かしいものを見るような気持ちになったり、
その世界に引き込まれて、時を忘れたりしてしまいます。
想像力をたくましくし、自在に情景を思い浮かべるのは楽しいものです。
写実的な表現に一幅の美しい絵を見ているような気持ちになったり、
滋味のある文体にしみじみとしたり、
ユーモアに富んだ言葉遣いに思わずほくそ笑んだり、
――そういう文章に出会えることは、本当に幸せなことです。
そのような文章を「心に残る名文」と題して、
ここに紹介していきます。
第20回 いろは和歌【と】 在原元方「年のうちに」『古今和歌集』より
2017-12-27

いろは和歌シリーズ、今回は「と」で始まる和歌を紹介します。
ふる年に春立ちける日よめる
在原元方
年のうちに春は来にけりひととせを去年とやいはむ今年とやいはむ
(『新編日本古典文学全集11 古今和歌集』小学館)
十二月のうちに立春を迎えた日に詠んだ歌
年内に春がやってきましたよ。この一年を去年と呼びましょうか、今年と呼びましょうか。
この和歌は、「古今和歌集」の冒頭に置かれています。
後世の人々からの評価は分かれているようですが、詞書を含め、年の変わり目や季節を表す言葉が集まっており、季節の移り変わりや節目を大切にする日本人らしい作品だと感じます。
詞書の「春立ちける日」とは立春のこと。
旧暦の立春は元日の前後となることが多く、そのため今も年賀状には「立春」「迎春」などと書くのです。当時の暦法では、年内に立春を迎える年が二年に一度くらいあったそうです。
真冬にお正月を迎える現代の私たちには、春はまだ遠いような気がします。でも、まだまだ寒いと思っているうち、あっという間に季節は移ろってゆくでしょう。
だからこそ節目ごとにその季節を感じ、一瞬一瞬を大切にしたいものです。
新しい年の春の空を、清々しい気持ちで見上げることができますように。
皆様、よいお年をお迎えください。
福井
第19回 太宰治『ヴィヨンの妻』
2017-08-25

太宰の全作品を網羅しているわけではありませんし、近代作品そのものの知識が決して多いとは言えない私ですが、太宰が描く女性は魅力的でとても好きです。ですので、今回は稚拙な知識ながら太宰治の『ヴィヨンの妻』を取り上げていきたいと思います。
『ヴィヨンの妻』は太宰が疎開先から東京の三鷹に帰ってきた1945(昭和21)年から、眠去する1948(昭和23)年までに書かかれた晩年の作品の一つです。主人公はさっちゃんという女性です。大谷という内縁の夫がいて、2人の間には息子がいます。しかし大谷は絵に描いたようなダメ男で、内縁とはいえ妻子がある身にも関わらず、酒に溺れ、金を使い、家に帰らず女のところに入り浸り……家庭を顧みることはなく、自分を守るためなら平気で嘘をつくような有様です。それに反し、さっちゃんは大谷を怒ることも拒絶することもしません。むしろ大谷を守っているところを見ると、太宰の理想の女性ともいいそうな、とてもけなげな女性です。しかし、ただ懐の広いけなげなだけの女性ではありません。物語が進むにつれて、そこに「したたかさ」が加わり、さっちゃんが確実に強くなっていくところがこの話の面白いところだと思います。
その変化が分かる場面の「台詞」を2つ取り上げたいと思います。
1つ目は大谷が金を盗んだことがきっかけで、その料理屋で働き始めたさっちゃんと一緒に家に帰る大谷の2人の会話の一節です。
「なぜ、はじめからこうしなかったのでしょうね。とっても私は幸福よ」
「女には、幸福も不幸もないものです」
「そうなの? そう言われると、そんな気もして来るけど、それじゃ、男の人は、どうなの?」
「男には、不幸だけがあるんです。いつも恐怖と、戦ってばかりいるのです」
(『ヴィヨンの妻』新潮文庫)
太宰特有の軽快な会話の中に、隠れた女性の強さと、男性の見栄が凝縮されています。そして、それまで好き放題やっている大谷を家で待つしかなかったさっちゃんが外で居場所を見つける一方、相変わらず変わらない大谷…2人の関係性の変化も垣間見ることができるおもしろい会話です。
2つ目はこの物語の象徴ともいえるさっちゃんが最後に吐くこの台詞です。
「人非人でもいいじゃないの。私たちは、生きてさえすればいいのよ。」(同上)
料理屋で働き始めたことで、さっちゃんの日々は前より楽しくなっていました。しかし、貧しい時代だったこともあり、さっちゃんは、この世の人は全員、夫に負けじと暗いところを持っていると思い始めます。そんなある日、さっちゃんは店の客に家まで着いてこられた上に、あっさり襲われてしまいます。次の日、何事もなかったかのように料理屋へ出向くと、そこにはすでに大谷がいました。しかし、さっちゃんは昨晩のことを大谷に話すことはなく、いつも通り大谷に接します。そんなさっちゃんに対し、大谷は雑誌に自分が「人非人」と書かれたことをぼやき、「ぼくはさっちゃんと息子のために金を盗んだんだから、人非人ではない」と言います。その大谷に対してさっちゃんが言った台詞です。どんな感情からこの台詞を吐いたのか。「あきらめ」「絶望」「自立」「愛情」「希望」……おそらく読む人によって様々な捉え方ができる一文だと思います。
太宰がさっちゃんを理想の女性として描いたのか真偽は分かりません。しかし、比較的男性が何でも強いとされていた時代に、自分(男性)のエゴや醜さをさらけ出すことで、女性の強さを描き出す太宰の作品には心惹かれるものがあります。
柴
第18回 いろは和歌【へ】 「へだてなき」紫式部『源氏物語』より
2017-07-27

いろは和歌シリーズ、今回は「へ」で始まる和歌を紹介します。
へだてなき心ばかりは通ふともなれし袖とはかけじとぞ思ふ
(岩波書店『新 日本古典文学大系22 源氏物語 四』「総角」)
隔てのない心だけは通っても、慣れ親しんで袖を重ねたなどとは口にすまいと思います
この和歌の読み手は、 大君と呼ばれる女性。『源氏物語』に登場する人物です。
それでは、この和歌が詠まれる前後の物語を、簡単にお話ししましょう。この和歌が出てくるのは「 総角」の巻。いわゆる「 宇治十帖」(光源氏没後、舞台を宇治に移してからの物語)の中の一巻です。
主な登場人物は、 薫中納言とその友人でありライバルでもある 匂宮( 帝の子)、それから大君と 中君の姉妹。姉妹の母親は早くに亡くなっており、半ば世を捨てたような暮らしをしていた父親も他界したばかり。
薫は大君に心ひかれて求愛しますが、大君は薫を受け入れようとせず、自分の代わりに妹の中君を薫と結婚させようとします。しかし薫は諦めません。姉妹に興味をもっていた色好みの匂宮をひそかに中君のもとへ案内し、自分は大君のもとへ忍び込みます。しかし、大君はやはり受け入れようとせず、薫はただ話をして夜を明かします。
ことのなりゆきにショックを受けながらも、大君は、匂宮と結ばれた妹のため母親がわりになって結婚の儀礼の世話をします。そこへ薫の和歌が届きます。
小夜衣きてなれきとはいはずともかことばかりはかけずしもあらじ
(同上)
夜着を着て慣れ親しんだとは言わなくとも、恨みごとくらいはかけないものでもありません
冒頭の和歌は、これに対する大君の返しです。
なれなれしくはしないでください、という意思表示だけではなく、後ろ盾のない境遇で妹と自身の運命を守っていこうと一生懸命な女性の気持ちが素直に表れているように感じられます。
大君はなぜここまで薫を拒むのでしょう。そして、彼らの恋愛模様はこのあとどうなるのでしょう。気になった方は、ぜひこれを機会に『源氏物語』を手にとってみてください。
福井
第17回 有島武郎『小さき者へ』1918(大正7)年
2017-06-16

日々の凄惨なニュースを見ていると、「子供を愛していない親なんていない」という使い古された言葉はどうやら真理ではないらしいということが、私にもなんとなく理解できてきた。それは、決して納得したくない事実ではあるが、しかし、だからこそ、我が子を思う親の愛情の尊さに胸を打たれることもある。
白樺派の中心的人物の一人だった有島武郎は、1916(大正5)年、最愛の妻・安子を肺結核で亡くした。残されたのは、三人の幼い息子たち。この子たちはこれから母なしで生きていかなければならない。
そんな子供たちを勇気づけるために書いたのが「小さき者へ」だと言われている。
お前たちが大きくなって、一人前の人間に育ち上った時、――その時までお前たちのパパは生きているかいないか、それは分らない事だが――父の書き残したものを繰拡げて見る機会があるだろうと思う。その時この小さな書き物もお前たちの眼の前に現われ出るだろう。時はどんどん移って行く。お前たちの父なる私がその時お前たちにどう映るか、それは想像も出来ない事だ。恐らく私が今ここで、過ぎ去ろうとする時代を嗤い憐れんでいるように、お前たちも私の古臭い心持を嗤い憐れむのかも知れない。私はお前たちの為めにそうあらんことを祈っている。お前たちは遠慮なく私を踏台にして、高い遠い所に私を乗り越えて進まなければ間違っているのだ。然しながらお前たちをどんなに深く愛したものがこの世にいるか、或はいたかという事実は、永久にお前たちに必要なものだと私は思うのだ。お前たちがこの書き物を読んで、私の思想の未熟で頑固なのを嗤う間にも、私たちの愛はお前たちを暖め、慰め、励まし、人生の可能性をお前たちの心に味覚させずにおかないと私は思っている。だからこの書き物を私はお前たちにあてて書く。
(『小さき者へ・生れ出ずる悩み』新潮文庫)
私の父は、武郎ほどあからさまに愛情深い人ではなかった。朝早く夜遅い人だったから、平日は顔を合わせることすらまれだった。そのうえ、休日も家でひたすら寝ていたから、思い出らしい思い出もそれほど多くない。
普段無口なくせに、大好きなプロ野球の観戦にいくと、外野席でわあわあと騒いでいた。
いつもはいくら駄々をこねても何も買ってくれないのに、たまに二人で釣りに行くと、妹たちに内緒でアイスを買ってくれた。
「おまえはお父さんとお母さんが海で遊んでいるときに、沖から流れてきたんだよ」とわけのわからないことを言って、私を怖がらせた。
――私の父もなかなかだと思う。
一方、武郎は『小さき者へ』を書いた数年後、十歳前後の息子たちを残して人妻と心中した。
さんざん、「おまえたちはこんなふうに生まれたんだよ。愛しているよ」みたいなことを書いておきながら、最終的には、男女の愛におぼれて、父としての自分を捨てた。
作品の価値は作者から独立していると思うが、どうしてもがっかりはしてしまう。
これでは、私の父の方がよっぽど立派だ。
――このくらいまで考えて、「有島武郎よりも私の父の方が立派だ」というのは、悪くない感想だと思った。
そうか、私の父は立派らしい。
話がそれてしまった。
武郎の父としての資質はさておき、作品は息子たちへの愛情にあふれている。
「お前たち」が生まれた日のエピソードから始まり、亡き妻がいかに「お前たち」を愛していたか、「私」がいかに「お前たち」を愛しているか――これからを生きる「お前たち」へのメッセージが、いかにも慈愛に満ちた言葉でつづられる。
よい文章を書いて、後世に残す――それは確かに、武郎にしかできない愛情表現だろう。
小さき者よ。不幸なそして同時に幸福なお前たちの父と母との祝福を胸にしめて人の世の旅に登れ。前途は遠い。そして暗い。然し恐れてはならぬ。恐れない者の前に道は開ける。
行け。勇んで。小さき者よ。
(同書)
まあ、私の父の方が立派なのだが。
瓜角
(肖像写真は国立国会図書館蔵)
第16回 夏目漱石 不惑の転職「入社の辞」
2017-05-08

自分に合う仕事を見つけるのは、なかなか難しいことですね。就職しても、どうしても肌に合わなくて、職場を変える人は少なくありません。
昭和の高度成長のころまでは、就職したら生涯の仕事と思って働くというのが、当然のように思われていました。しかし、近ごろは職種も多く、条件が合えば、転職するのはそれほど苦ではないような時代になっているようです。そのせいか、「近いうち転職するんだ」などと言う人に会っても、以前のように重大なこととして驚かなくなりました。
自分に向かない仕事を無理してやっているよりも、やりたい仕事に精を出すほうが、はるかに幸せなことに違いありません。
その先駆者ともいえる、思い切った大転身を試みたのが夏目漱石です。
『吾輩は猫である』や『坊ちゃん』、『草枕』を発表し、一躍人気作家になっていた漱石が、40歳、不惑の年のことです。朝日新聞社から入社の依頼がありました。入社して、長編小説を新聞に書いてくれれば、月給200円出そうというのです。
東京帝国大学英文科講師として67円の月給をもらっていた漱石でしたが、ちょうどそのとき、大学から月給150円で教授に昇格しようという話も持ち上がっていたのです。さあ、漱石は迷いました。
悩んだ末に決めたのは、小説を書くという仕事でした。教授になれば定年まで安泰ですが、授業が増えて小説を書く時間がなくなります。新聞社は民間企業で、いつまで身分を保証してくれるかわかりませんが、好きな小説を好きなときに書けるのです。
乾坤一擲、大学に辞表を届け、『入社の辞』を朝日新聞に発表しました。次に紹介するのは、その冒頭です。
大学を辞して朝日新聞にはいったら逢う人が皆驚いた顔をしている。なかにはなにゆえだと聞くものがある。大決断だと褒めるものがある。大学をやめて新聞屋になることがさほどに不思議な現象とは思わなかった。余が新聞屋として成功するかせぬかはもとより疑問である。成功せぬことを予期して十余年の径路を一朝に転じたのを無謀だと言って驚くならもっともである。かく申す本人すらその点については驚いている。しかしながら大学のような栄誉ある位置を抛って、新聞屋になったから驚くというならば、やめてもらいたい。大学は名誉ある学者の巣を喰っている所かもしれない。尊敬に価する教授や博士が穴籠もりをしている所かもしれない。二三十年辛抱すれば勅任官になれる所かもしれない。その他いろいろ便宜のある所かもしれない。なるほどそう考えてみると結構な所である。赤門を潜り込んで、講座へはい上がろうとする候補者は――勘定してみないから、幾人あるか分からないが、いちいち聞いて歩いたらよほどひまを潰すくらいに多いだろう。大学の結構なことはそれでも分かる。余も至極御同意である。しかし御同意というのは大学が結構な所であるということに御同意を表したのみで、新聞屋が不結構な職業であるということに賛成の意を表したんだと早合点をしてはいけない。(以下略)
1907(明治40)年5月3日付東京朝日新聞
(『夏目漱石全集 第四巻』角川書店)
明治40年には、東京、京都に次いで東北帝国大学が創設されましたが、当時大学に通えるのはほんのひと握りでした。その教授となればなおさら、なりたくてもおいそれとなれる職業ではありません。「大学のような栄誉ある位置を抛って、新聞屋になったから驚くというならば、やめてもらいたい」と言われても、やはり驚かざるを得ませんね。
明治30年、読売新聞に連載された尾崎紅葉の『金色夜叉』は大人気を博しました。新聞の読者は、本を買って読む人に比べたらはるかに多いわけですから、新聞連載は普通に本を出すよりはるかに影響力が大きかったのです。漱石がどれほど入社後第一作目の『虞美人草』に力をそそいだかは想像に難くないことです。 そして、その美しい文章が評判となって、三越呉服店からは浴衣地が、玉栄堂という宝石店からは指環が「虞美人草」の名を冠して売り出されたということです。
いずれにしても、自分の好きなことを生涯の生業にできることほど、幸せなことはありません。日々の積み重ねで、少しずつ成長していけることも大事なことですね。私も、縁の下の力持ちである編集という仕事を誇りに思って、精進していきたいと思います。
清し女