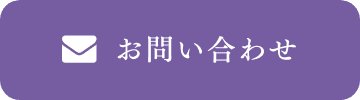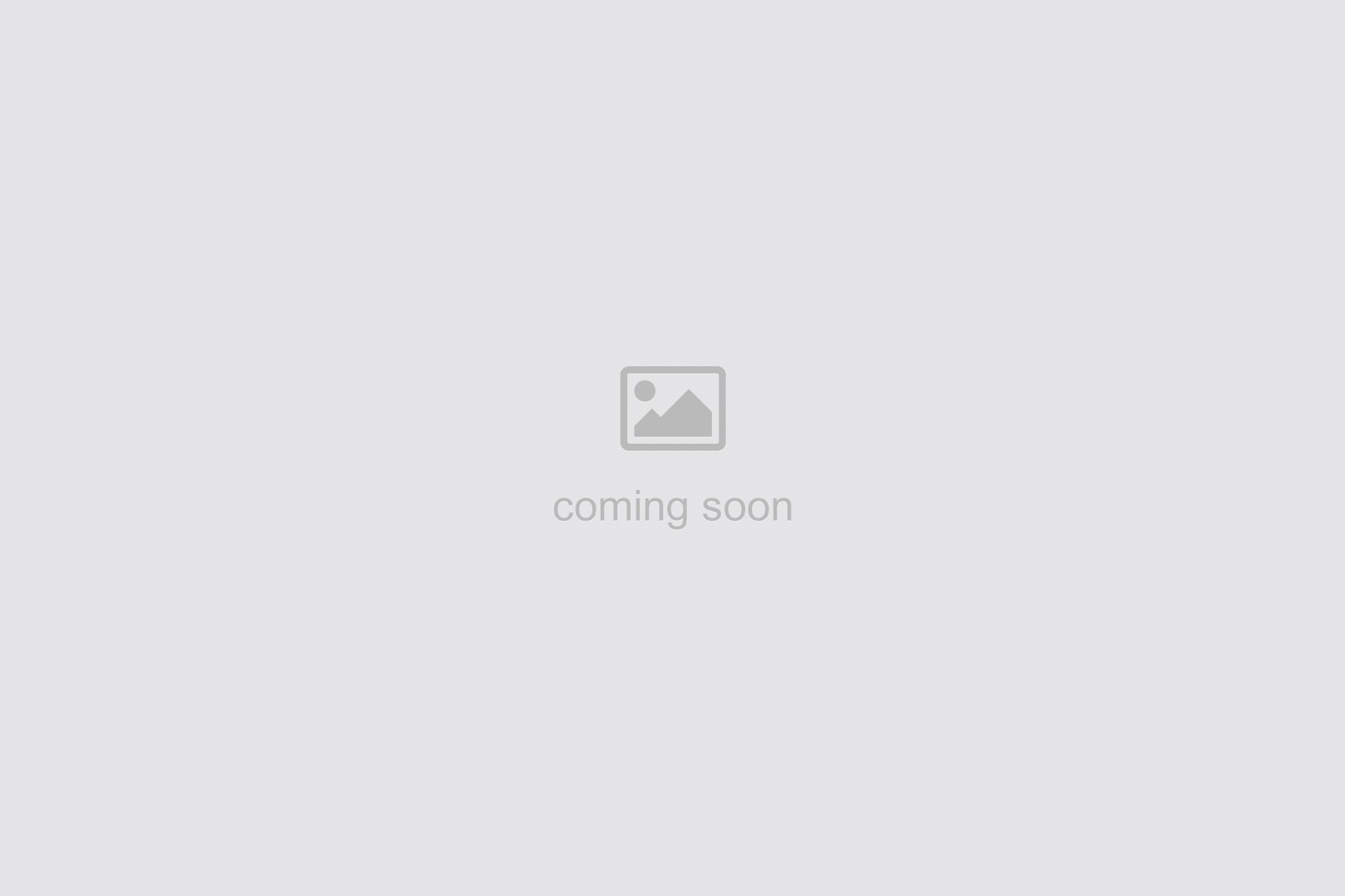心に残る名文

小説や随筆などを読んでいると、
「これは名文中の名文だな」と思う場面に出会うことがあります。
ありありと情景が目に浮かび、懐かしいものを見るような気持ちになったり、
その世界に引き込まれて、時を忘れたりしてしまいます。
想像力をたくましくし、自在に情景を思い浮かべるのは楽しいものです。
写実的な表現に一幅の美しい絵を見ているような気持ちになったり、
滋味のある文体にしみじみとしたり、
ユーモアに富んだ言葉遣いに思わずほくそ笑んだり、
――そういう文章に出会えることは、本当に幸せなことです。
そのような文章を「心に残る名文」と題して、
ここに紹介していきます。
第30回 いろは和歌【よ】 在原業平「世の中に」『伊勢物語』より
2022-04-06

いろは和歌シリーズ、今回は「よ」で始まる一首を紹介します。
世の中にたえて櫻のなかりせば春の心はのどけからまし
(岩波書店「伊勢物語」)
この世の中に、まったく桜というものがなかったなら、春の人の心はのどかであったことでしょう。
桜を詠んだ和歌の中でも、有名な一首でしょう。『古今和歌集』にも採られています。
『伊勢物語』の八十二段、惟喬親王の別邸である渚の院で「馬の頭なりける人」=在原業平(825年―880年)によって詠まれた歌として登場します。
日本の春の象徴として咲き誇る桜、花盛りにあってもどこか陰りのつきまとう桜、時に怪異を生む桜、あっというまに散っていく桜。
桜にはさまざまな文学上のイメージがありますが、現代の私たちも、無意識にそれらを背負って桜を見上げているのかもしれません。
第29回 いろは和歌【か】 藤原家経「風越の」『詞花和歌集』より
2022-04-05

いろは和歌シリーズ、今回は「か」で始まる一首を紹介します。
信濃の守にて下りけるに、風越の峰にて 藤原家経朝臣
風越の峰のうへにてみる時は雲はふもとのものにぞありける (岩波書店「詞花和歌集」)
風越山の峰の上で見るときには、雲は山の麓のものだったのですね。
風越は歌枕(和歌の題材となる名所旧跡)で、現在の長野県にある風越山のこと。
詞書にあるように、作者である藤原家経(992年―1058年)が信濃の守として任地に赴いた際の歌です。
現在の風越山は、標高1535メートル。「峰」は山頂やその付近のことをいいます。
普段空にあるものとして見ていた雲が麓にあるものとして見えた、という気づきは、その場に身を、または心を置いたときにこそ得られるものでしょう。
福井
第28回 いろは和歌【わ】 参議篁「わたの原」『古今和歌集』より
2022-03-07

いろは和歌シリーズ、今回は「わ」で始まる一首を紹介します。
わたの原 八十島 かけて漕ぎ出ぬと人には告げよ 海士 の釣り舟
(岩波書店「古今和歌集」)
(私は)海原に多くの島を目指して漕ぎ出していったと、人に告げておくれ、漁師の釣り船よ。
小倉百人一首に収められている一首。
「参議篁」は官位による呼び名で、作者の名は小野篁(802年―853年)。
漢詩や書に優れ、政務にも長けた人物でした。
昼は朝廷で、夜は冥府の 閻魔 大王のもとで仕事をしていたという伝説もあり、『 今昔物語集 』などの説話集にもその名が登場します。
この歌は、作者が天皇の怒りにふれ、流罪にあった折に都の親しい人を思って詠んだものとされます。
広い海にぽつんと浮かぶ舟という景色から、作者の孤独と強い念とが伝わってくるようです。
福井
第27回 いろは和歌【を】 藤原頼道「折られけり」『新古今和歌集』より
2022-02-21

いろは和歌シリーズ、今回は「を」で始まる一首を紹介します。
題しらず 宇治前関白太政大臣頼通
折られけりくれなゐ匂ふ梅の花今朝しろたへに雪は降れれど
(岩波書店「新古今和歌集」)
折ることができましたよ、紅の美しい梅の花を。今朝は雪が真っ白に降っていますけれど。
「折る」は現代かなづかいでは「おる」と書きますが、歴史的かなづかいでは「をる」と書きます。
作者は 藤原 頼道 (992年―1074年)。平安時代に栄華を極めた藤原道長の長男で、平等院鳳凰堂を造営した人物です。
梅の花は、まだ雪の積もるころに咲き出します。
梅の紅と雪の白。対照的な色彩が鮮やかな一首といえるでしょう。
倒置法によって強調された梅の花の美しさ、清らかさが印象的です。
福井
第26回 いろは和歌【る】 和泉式部「瑠璃の地と」『和泉式部集』より
2022-02-07

いろは和歌シリーズ、今回は「る」で始まる一首を紹介します。
瑠璃 の地と人もみつべしわが 床 は涙の玉と敷きに敷ければ (岩波書店「和泉式部歌集」)
瑠璃の地と人も見るに違いありません、私の寝床は、涙が玉のように敷き詰められていますので。
この歌は、第4回【ろ】で紹介した、
櫓もおさで風にまかするあま舟のいづれのかたによらんとすらん
が含まれる四十三首の歌群の中の一つです。
「瑠璃の地」とは、極楽浄土のこと。
涙が玉のように敷き詰められたイメージは美しく、また、人の命や思いのはかなさを想起させます。
作者の体はまだこの世にあるけれど、魂はすでに遠く離れた場所にあるのかもしれません。
福井