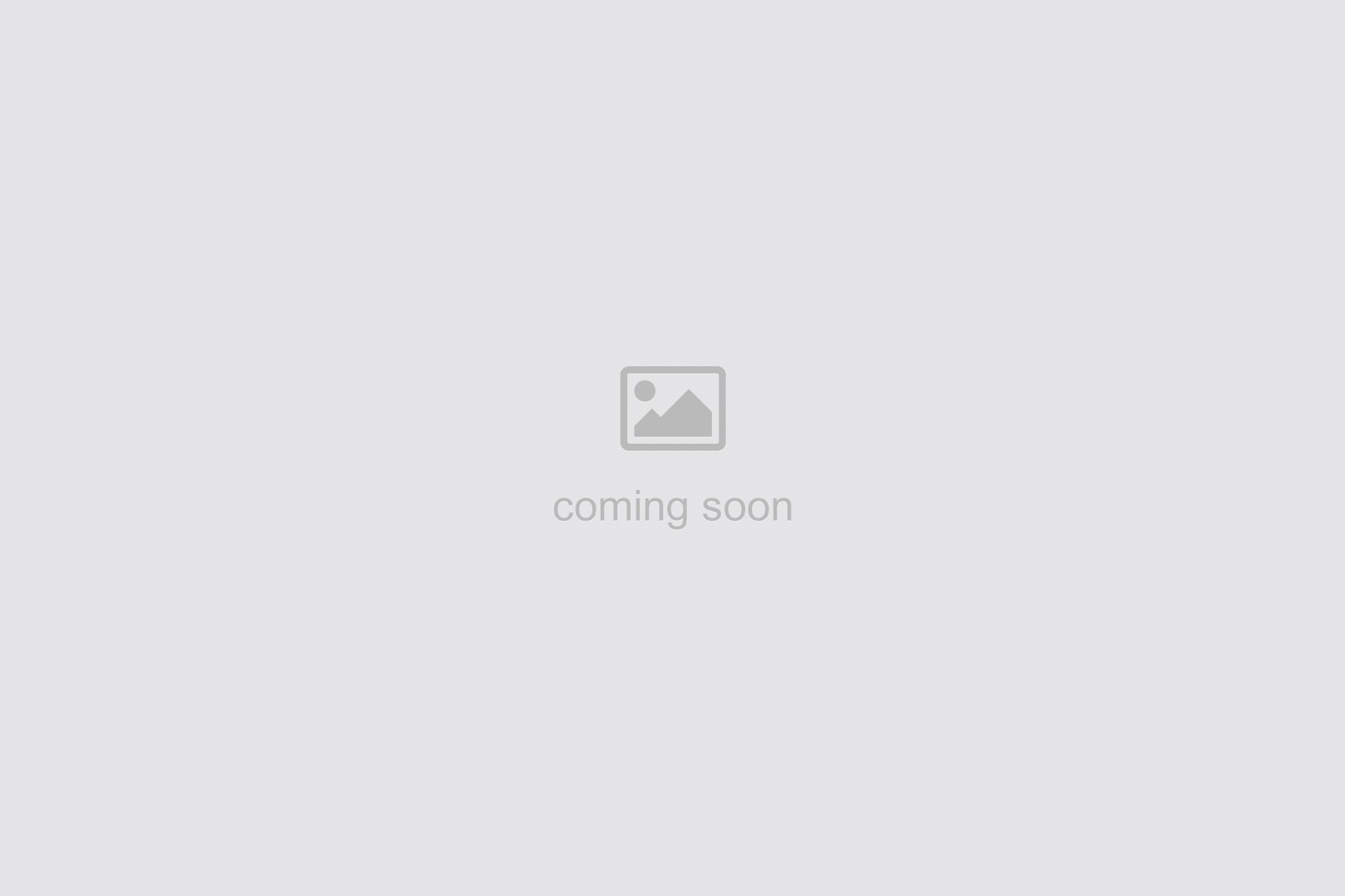心に残る名文
第16回 夏目漱石 不惑の転職「入社の辞」
2017-05-08

自分に合う仕事を見つけるのは、なかなか難しいことですね。就職しても、どうしても肌に合わなくて、職場を変える人は少なくありません。
昭和の高度成長のころまでは、就職したら生涯の仕事と思って働くというのが、当然のように思われていました。しかし、近ごろは職種も多く、条件が合えば、転職するのはそれほど苦ではないような時代になっているようです。そのせいか、「近いうち転職するんだ」などと言う人に会っても、以前のように重大なこととして驚かなくなりました。
自分に向かない仕事を無理してやっているよりも、やりたい仕事に精を出すほうが、はるかに幸せなことに違いありません。
その先駆者ともいえる、思い切った大転身を試みたのが夏目漱石です。
『吾輩は猫である』や『坊ちゃん』、『草枕』を発表し、一躍人気作家になっていた漱石が、40歳、不惑の年のことです。朝日新聞社から入社の依頼がありました。入社して、長編小説を新聞に書いてくれれば、月給200円出そうというのです。
東京帝国大学英文科講師として67円の月給をもらっていた漱石でしたが、ちょうどそのとき、大学から月給150円で教授に昇格しようという話も持ち上がっていたのです。さあ、漱石は迷いました。
悩んだ末に決めたのは、小説を書くという仕事でした。教授になれば定年まで安泰ですが、授業が増えて小説を書く時間がなくなります。新聞社は民間企業で、いつまで身分を保証してくれるかわかりませんが、好きな小説を好きなときに書けるのです。
乾坤一擲、大学に辞表を届け、『入社の辞』を朝日新聞に発表しました。次に紹介するのは、その冒頭です。
大学を辞して朝日新聞にはいったら逢う人が皆驚いた顔をしている。なかにはなにゆえだと聞くものがある。大決断だと褒めるものがある。大学をやめて新聞屋になることがさほどに不思議な現象とは思わなかった。余が新聞屋として成功するかせぬかはもとより疑問である。成功せぬことを予期して十余年の径路を一朝に転じたのを無謀だと言って驚くならもっともである。かく申す本人すらその点については驚いている。しかしながら大学のような栄誉ある位置を抛って、新聞屋になったから驚くというならば、やめてもらいたい。大学は名誉ある学者の巣を喰っている所かもしれない。尊敬に価する教授や博士が穴籠もりをしている所かもしれない。二三十年辛抱すれば勅任官になれる所かもしれない。その他いろいろ便宜のある所かもしれない。なるほどそう考えてみると結構な所である。赤門を潜り込んで、講座へはい上がろうとする候補者は――勘定してみないから、幾人あるか分からないが、いちいち聞いて歩いたらよほどひまを潰すくらいに多いだろう。大学の結構なことはそれでも分かる。余も至極御同意である。しかし御同意というのは大学が結構な所であるということに御同意を表したのみで、新聞屋が不結構な職業であるということに賛成の意を表したんだと早合点をしてはいけない。(以下略)
1907(明治40)年5月3日付東京朝日新聞
(『夏目漱石全集 第四巻』角川書店)
明治40年には、東京、京都に次いで東北帝国大学が創設されましたが、当時大学に通えるのはほんのひと握りでした。その教授となればなおさら、なりたくてもおいそれとなれる職業ではありません。「大学のような栄誉ある位置を抛って、新聞屋になったから驚くというならば、やめてもらいたい」と言われても、やはり驚かざるを得ませんね。
明治30年、読売新聞に連載された尾崎紅葉の『金色夜叉』は大人気を博しました。新聞の読者は、本を買って読む人に比べたらはるかに多いわけですから、新聞連載は普通に本を出すよりはるかに影響力が大きかったのです。漱石がどれほど入社後第一作目の『虞美人草』に力をそそいだかは想像に難くないことです。 そして、その美しい文章が評判となって、三越呉服店からは浴衣地が、玉栄堂という宝石店からは指環が「虞美人草」の名を冠して売り出されたということです。
いずれにしても、自分の好きなことを生涯の生業にできることほど、幸せなことはありません。日々の積み重ねで、少しずつ成長していけることも大事なことですね。私も、縁の下の力持ちである編集という仕事を誇りに思って、精進していきたいと思います。
清し女