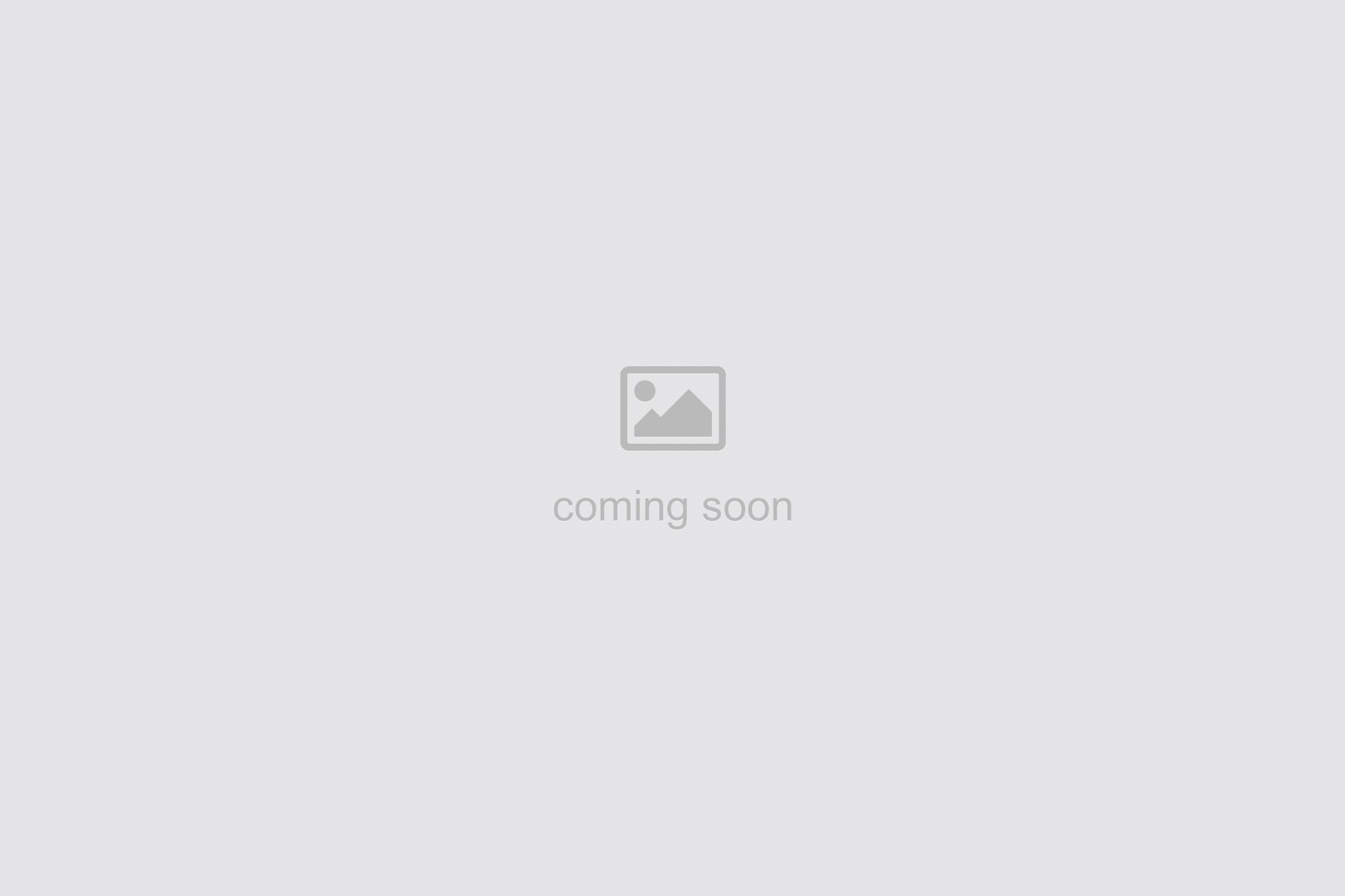心に残る名文
第7回 芥川龍之介『大川の水』1914(大正3)年
2016-12-06

本年も早いもので師走となり、残すところわずかとなりました。2016年は、小説『鼻』が『新思潮』に「芥川龍之介」の署名で掲載されてから百年目という記念すべき年でした。今回は、この芥川の随筆をご紹介したいと思います。
芥川は、現在の東京都墨田区両国の大川―隅田川の吾妻橋から下流部の通称―の近くで育ちました。幼年時代、毎日のように目にする風景に大川があったわけです。「自分はどうして、かうもあの川を愛するのか。」――大川への愛を記した文章が『大川の水』です。
(略)自分を魅するものは独り大川の水の響ばかりではない。自分にとつては、此川の水の光が殆、何処にも見出し難い、滑さと暖さとを持つてゐるやうに思はれるのである。
海の水は、たとへば碧玉の色のやうに余りに重く緑を凝してゐる。と云つて潮の満干を全く感じない上流の川の水は、云はゞ緑柱石の色のやうに、余りに軽く、余りに薄つぺらに光りすぎる。唯淡水と潮水とが交錯する平原の大河の水は、冷な青に、濁つた黄の暖みを交へて、何処となく人間化された、親しさと、人間らしい意味に於て、ライフライクな、なつかしさがあるやうに思はれる。殊に大川は、赭ちやけた粘土の多い関東平野を行きつくして、「東京」と云ふ大都会を静に流れてゐるだけに、其濁つて、皺をよせて、気むづかしい猶太の老爺のやうに、ぶつぶつ口小言を云ふ水の色が、如何にも落付いた、人なつかしい、手ざはりのいゝ感じを持つてゐる。さうして、同じく市の中を流れるにしても、猶「海」と云ふ大きな神秘と絶えず、直接の交通を続けてゐる為か、川と川とをつなぐ堀割の水のやうに暗くない。眠つてゐない。何処となく、生きて動いてゐると云ふ気がする。しかも其動いてゆく先は、無始無終に亘る「永遠」の不可思議だと云ふ気がする。
(『芥川龍之介全集 第一巻』岩波書店)
※旧字体は新字体に改めた。
一読してみていかがでしょうか。巧みな情景描写と比喩表現を味わっていただけたでしょうか。若干22歳の若者が書いたと思うと、その溢れ出る才能に胸が高鳴ります。
海や上流の川の水を、宝石という一般から離れたものにたとえることで、大川の水の親しみやすさや人間らしさを強調しています。宝石のような澄んだ美しさはなく、むしろ濁ってすらいるけれども、その濁りこそが生活感を感じさせ、暖かいといっているのです。また、猶太の老爺の比喩表現は、一際優れていて、目前にその様子が浮かんでくるようです。
芥川の大川への愛は、引用部にとどまりません。「どうして、かうもあの川を愛するのか。」是非その理由を、全文読んでみてください。
1-11-1