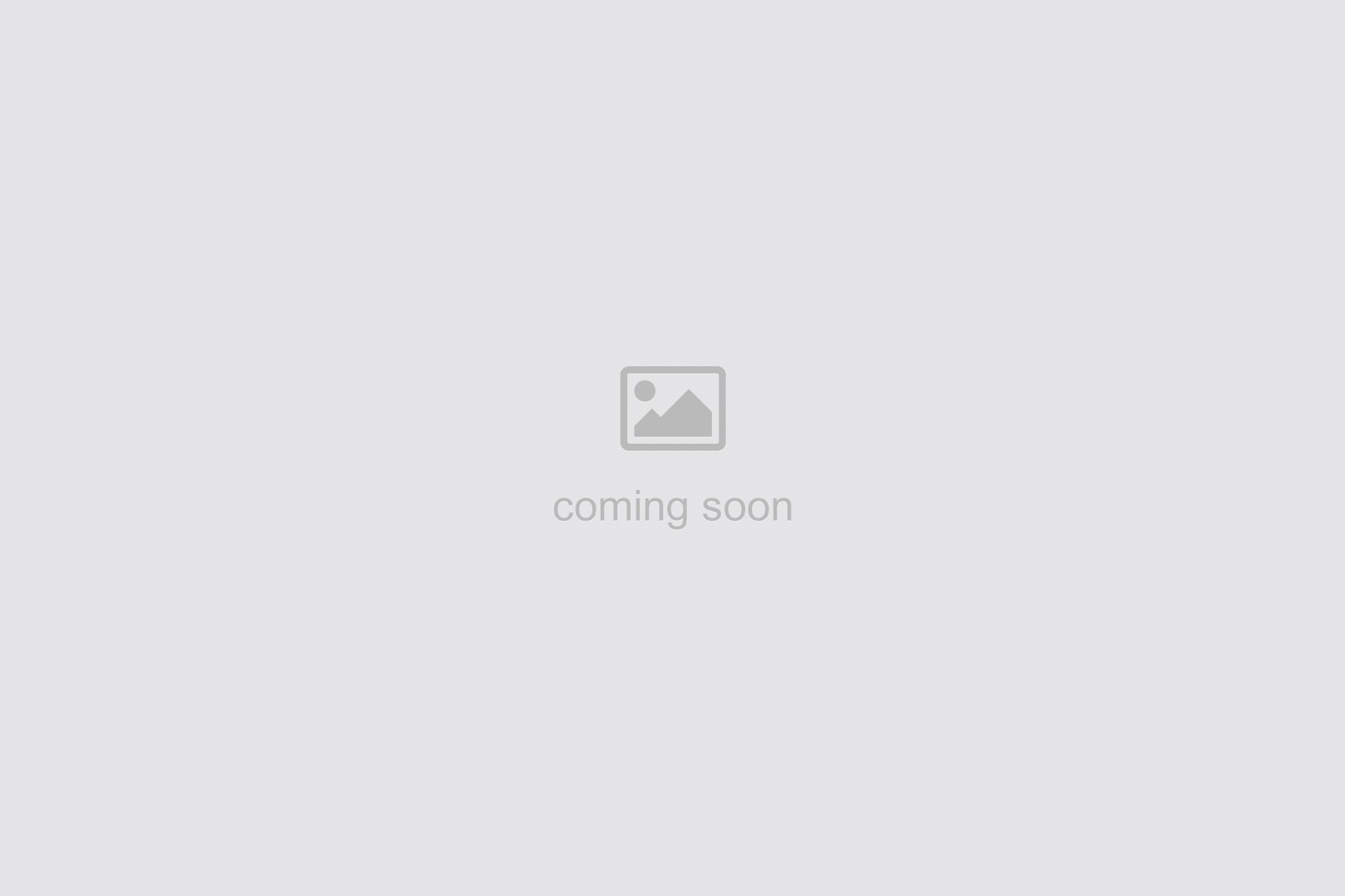心に残る名文

小説や随筆などを読んでいると、
「これは名文中の名文だな」と思う場面に出会うことがあります。
ありありと情景が目に浮かび、懐かしいものを見るような気持ちになったり、
その世界に引き込まれて、時を忘れたりしてしまいます。
想像力をたくましくし、自在に情景を思い浮かべるのは楽しいものです。
写実的な表現に一幅の美しい絵を見ているような気持ちになったり、
滋味のある文体にしみじみとしたり、
ユーモアに富んだ言葉遣いに思わずほくそ笑んだり、
――そういう文章に出会えることは、本当に幸せなことです。
そのような文章を「心に残る名文」と題して、
ここに紹介していきます。
第10回 清少納言『枕草子』第二八〇段「雪のいと高う降りたるを」
2017-01-30

寒い冬、『枕草子』は第一段「春はあけぼの」と同様に有名な「雪のいと高う降りたるを」を鑑賞するのはいかがでしょう。
この段の人気の秘密は、簡潔でわかりやすく、清少納言と中宮定子の才女ぶりが、浮き彫りにされているところにあるのではないでしょうか。
一条天皇の正室である中宮定子は才色兼備の人。10歳も年上の清少納言は、定子が18歳のときから死去するまで彼女に仕えました。『枕草子』の中にも、定子にかかわる話題が多くつづられています。
ある雪の降る日のできごとです。明朗快活で聡明な定子は、「ただ雪見をするのはつまらない、何か面白い趣向はないものか」と思案し、思いついたのが白居易(白楽天)の漢詩の一句を女房に投げかけて返答させるというものでした。
「だれもが知っているその句に謎をかけ、だれかに応えてもらったら面白いわ」そう思った定子が、多く侍る女房の中から白羽の矢を立てたのが、学才にたけ機転の利く、清少納言だったのです。定子は、果たして少納言がどのように返してくれるかしらと、内心ワクワクしながら楽しんでいたのではないかと思うと、こちらまでそのワクワク感が伝わってくるようで楽しくなります。
雪のいと高う降りたるを、例ならず御格子まゐりて、炭櫃に火おこして、物語などしてあつまりさぶらふに、「少納言よ。香炉峰の雪いかならむ」と仰せらるれば、御格子上げさせて、御簾を高く上げたれば、笑はせたまふ。人々も「さる事は知り、歌などにさへうたへど、思ひこそよらざりつれ。なほこの宮の人にはさべきなめり」と言ふ。
(『新編 日本古典文学全集 18』小学館)
※読みやすさを考慮し、ルビは現代仮名遣いにしています。
(現代語訳)
雪が大変深く降り積もっているのを、いつになく御格子を下ろしたままで、炭櫃に火を起こして、私たち女房が話などをして集まって伺候していると、中宮様が「少納言よ。香炉峰の雪はどんなであろう」と仰せになるので、女官に御格子を上げさせて、御簾を高く巻き上げたところ、お笑いあそばす。周りの人々も「白楽天のその詩句は知っていて、歌などにまで読み込むのだけれど、中宮様の謎かけとは思いもしなかったわ。(とっさに御簾を上げた少納言のように、)やはり、この宮にお仕えする人としては、そうあるべきなのね」と言う。
そう、「簾を上げる」が正解だったのです。
白居易はエリート官僚でしたが、あることから左遷され、景勝地である香炉峰のふもとに新居を構えました。そのときに詠んだ詩の中に、この詩句があります。
香炉峰下、新たに山居を卜し、草堂初めて成り、偶たま東壁に題す
日高く眠り足りて猶起くるにもの慵し
小閣に衾を重ねて寒さを怕れず
遺愛寺の鐘は枕を欹てて聴き
香炉峰の雪は簾を撥げて看る
匡蘆は便ち是れ名を逃るるの地
司馬は仍お老いを送るの官為り
心泰く身寧きは是れ帰する処
故郷 何ぞ独り長安にのみ在らんや
『中国古典詩聚花』小学館
※現代仮名遣いで書き下しています。
詩全体を意訳しますと、「日は高く昇っているが、布団の中で、遺愛寺の鐘が響くと枕をずらして耳を澄まし、香炉峰の雪は簾を跳ね上げさせて眺め入る。ここは、俗世間から離れ住むにはふさわしい土地で、閑職とはいえ心が安らかであれば、それ以上何を望むことがあろう。長安だけが故郷ではあるまい。」 というような内容です。
少納言は定子の謎かけに、言葉で応える代わりに、御簾を巻き上げて見せました。その機転の利くしぐさに、定子は満足の笑みを返したのでした。
この日、清少納言が味わった、お慕いする人から認められる喜びは、どのようなものだったでしょうか。人と人との交わりの中で、相手から認められ、得も言われぬ喜びを感じる、そんな思い出をもって生きられるということは、どれほど幸せなことでしょう。その相手が敬慕する人であれば、なおのこと。
清し女
第9回 谷崎潤一郎『陰翳礼讃』1933(昭和8)年
2016-12-20

陰翳の陰も翳も、日の光が当たらないところ、おおわれて見えないところという意味で、転じて、含みや深みがあることをいいます。
谷崎の代表作の一つである『陰翳礼讃』は、日本の伝統美が、陰翳の美しさから成り立っていることを、あらゆる角度から見つめ、見直し、ほめたたえた評論です。こう書くと、何だか難しいことが堅苦しい文体で書かれているように思いますが、それはこの難しい漢字から受ける印象であって、中身は至って平易でわかりやすく、身近な例を挙げながら流麗な文章で書かれているので、一気に読んでしまえる作品です。
例えば、日本の家屋は陰翳と深いかかわりからできており、そこには切っても切れない照明の効果的な使い方があることや、漆器が和食に適していること、その他、和紙、織物、衣装、舞台、日本人の肌の色、女性の肉体、化粧法のことなど、光と影のコントラストが生み出す日本ならではの幻想的美しさを、ていねいに解き明かしているのです。
作品のどこを切り取っても、造詣の深さと品位の高い文体に舌を巻くばかりですが、以下、和食と器について語っている部分を引用してみます。
日本の料理は食うものでなくて見るものだと云われるが、こう云う場合、私は見るものである以上に瞑想するものであると云おう。そうしてそれは、闇にまたゝく 蠟 燭 の灯と漆の器とが合奏する無言の音楽の作用なのである。かつて漱石先生は「草枕」の中で羊羹の色を讃美しておられたことがあったが、そう云えばあの色などはやはり瞑想的ではないか。玉のように半透明に曇った肌が、奥の方まで日の光りを吸い取って夢みる如きほの明るさを啣んでいる感じ、あの色あいの深さ、複雑さは、西洋の菓子には絶対に見られない。クリームなどはあれに比べると何と云う浅はかさ、単純さであろう。だがその羊羹の色あいも、あれを塗り物の菓子器に入れて、肌の色が辛うじて見分けられる暗がりに沈めると、ひとしお瞑想的になる。人はあの冷たく滑かなものを口中にふくむ時、あたかも室内の暗黒が一箇の甘い塊になって舌の先で融けるのを感じ、ほんとうはそう旨くない羊羹でも、味に異様な深みが添わるように思う。けだし料理の色あいは何処の国でも食器の色や壁の色と調和するように工夫されているのであろうが、日本料理は明るい所で白ッちゃけた器で食べては慥かに食慾が半減する。
(中略)
また白味噌や、豆腐や、蒲鉾や、とろゝ汁や、白身の刺身や、あゝ云う白い肌のものも、周囲を明るくしたのでは色が引き立たない。第一飯にしてからが、ぴかぴか光る黒塗りの飯櫃に入れられて、暗い所に置かれている方が、見ても美しく、食慾をも刺戟する。あの、炊きたての真っ白な飯が、ぱっと蓋を取った下から煖かそうな湯気を吐きながら黒い器に盛り上って、一と粒一と粒真珠のようにかゞやいているのを見る時、日本人なら誰しも米の飯の有難さを感じるであろう。かく考えて来ると、われわれの料理が常に陰翳を基調とし、闇と云うものと切っても切れない関係にあることを知るのである。
(谷崎潤一郎『陰翳礼讃』中央公論新社)
この文章が書かれた昭和初期から80年以上もたった今日、私たちは便利で快適な生活に慣れ切って、陰翳のある生活などほとんど失ってしまったような気がします。しかし、谷崎の言うほどの深みはわからないまでも、和食が陰翳と調和するというのは、普遍の真理に違いないことだけはうなずけます。単調で明るいだけの蛍光灯の下では、どんなに美味なる和のお膳といえども、食慾が半減するに決まっていますし、間接照明や障子などで採光を加減するなどして、はじめて料理がおいしそうに目に映え、安心して箸を手に取る気になるものですから。
『陰翳礼讃』は、日本には陰翳を大切にするという奥ゆかしい生活習慣があったことを、再認識させてくれる一冊です。若いころ読んだときにはそれほど気にならなかった細やかな気配りが、日本の家屋や風習にはたくさんあることを改めて納得させられた思いです。日ごろのあわただしさから解放され、少しでもゆとりをもつためにも、日常のどこかに新しい陰翳の美を取り入れ、奥ゆかしさの一端を模索してみたい気がいたします。
清し女
第8回 いろは和歌【は】 太田垣蓮月「はらはらと」『海人の刈藻』より
2016-12-13

いろは和歌シリーズ、今回は「は」で始まる和歌を紹介します。
第6回で、坂本龍馬の手紙が紹介されましたね。今回紹介するのは、龍馬と同じ時代に生きた女性の作品です。
太田垣蓮月
秋山
はらはらとおつる木のはにまじりきて栗のみひとり土に声あり
(角川書店『新編国歌大観』)
はらはらと散る木の葉にまじって、栗の実だけがひとり地上に落ちて音を立てる――晩秋の山麓、栗の実が落ちる音だけが耳に届くような静寂の中に、作者が一人でたたずんでいる様子が浮かびます。
太田垣蓮月は、江戸時代後期から明治初期の女流歌人。寛政3(1791)年に京都に生まれ、明治8(1875)年に没した彼女の人生は波乱万丈でした。
生まれてすぐに養子に出され、やがて結婚するも夫と三人の子供を次々に亡くし、二度目の結婚をしますがその夫も病没。出家して養父とともに暮らしていましたが、やがてその養父も亡くなってしまい、天涯孤独の身になります。
その後は単身、京都の山麓を転々としながら、自作の和歌を彫りつけた焼き物を売って生活していたそうです。これは「蓮月焼」と呼ばれて京都土産として人気を博し、後に贋作が出回るほどだったとか。
蓮月にはいくつもの逸話が残っています。容貌が美しかったので出家してからも言い寄る男性が絶えなかったとか、それを避けるために自ら前歯を抜いて器量を悪くしようとしたとか、幕末の志士たちと親交があったとか、歌集を出すのを嫌がって出版には一切関知しなかったとか、上の和歌が収録されている歌集『海人の刈藻』が出来上がって送られてきたのを見て「二首ばかりは私の知らぬ歌も有る様子に御座候。」と言ったとか。
どれがどこまで本当のことかはわかりませんが、蓮月の人柄を想像させるエピソードです。
少しだけ蓮月のことを知ってから和歌に戻ってみると、栗の実を「ひとり」といい、それが落ちる音を「声」と表現していることに改めて気づきます。栗の実をまるで人間であるかのように描いたその思いは、どのようなものだったのでしょう。孤独を受け入れて穏やかな心境でいたかもしれないし、人恋しい思いに苦しんでいたかもしれません。
彼女がどんな女性だったのか、この和歌の景色の中に立つ彼女は何を思っていたのか、知れば知るほどもっと知りたくなってきます。
福井
第7回 芥川龍之介『大川の水』1914(大正3)年
2016-12-06

本年も早いもので師走となり、残すところわずかとなりました。2016年は、小説『鼻』が『新思潮』に「芥川龍之介」の署名で掲載されてから百年目という記念すべき年でした。今回は、この芥川の随筆をご紹介したいと思います。
芥川は、現在の東京都墨田区両国の大川―隅田川の吾妻橋から下流部の通称―の近くで育ちました。幼年時代、毎日のように目にする風景に大川があったわけです。「自分はどうして、かうもあの川を愛するのか。」――大川への愛を記した文章が『大川の水』です。
(略)自分を魅するものは独り大川の水の響ばかりではない。自分にとつては、此川の水の光が殆、何処にも見出し難い、滑さと暖さとを持つてゐるやうに思はれるのである。
海の水は、たとへば碧玉の色のやうに余りに重く緑を凝してゐる。と云つて潮の満干を全く感じない上流の川の水は、云はゞ緑柱石の色のやうに、余りに軽く、余りに薄つぺらに光りすぎる。唯淡水と潮水とが交錯する平原の大河の水は、冷な青に、濁つた黄の暖みを交へて、何処となく人間化された、親しさと、人間らしい意味に於て、ライフライクな、なつかしさがあるやうに思はれる。殊に大川は、赭ちやけた粘土の多い関東平野を行きつくして、「東京」と云ふ大都会を静に流れてゐるだけに、其濁つて、皺をよせて、気むづかしい猶太の老爺のやうに、ぶつぶつ口小言を云ふ水の色が、如何にも落付いた、人なつかしい、手ざはりのいゝ感じを持つてゐる。さうして、同じく市の中を流れるにしても、猶「海」と云ふ大きな神秘と絶えず、直接の交通を続けてゐる為か、川と川とをつなぐ堀割の水のやうに暗くない。眠つてゐない。何処となく、生きて動いてゐると云ふ気がする。しかも其動いてゆく先は、無始無終に亘る「永遠」の不可思議だと云ふ気がする。
(『芥川龍之介全集 第一巻』岩波書店)
※旧字体は新字体に改めた。
一読してみていかがでしょうか。巧みな情景描写と比喩表現を味わっていただけたでしょうか。若干22歳の若者が書いたと思うと、その溢れ出る才能に胸が高鳴ります。
海や上流の川の水を、宝石という一般から離れたものにたとえることで、大川の水の親しみやすさや人間らしさを強調しています。宝石のような澄んだ美しさはなく、むしろ濁ってすらいるけれども、その濁りこそが生活感を感じさせ、暖かいといっているのです。また、猶太の老爺の比喩表現は、一際優れていて、目前にその様子が浮かんでくるようです。
芥川の大川への愛は、引用部にとどまりません。「どうして、かうもあの川を愛するのか。」是非その理由を、全文読んでみてください。
1-11-1
第6回 坂本龍馬の手紙 文久3(1863)年6月29日付 坂本乙女宛
2016-11-15

「右の事ハ、まづまづ あいだがらにも すこしもいうては、見込のちがう人あるからは、をひとりニて御聞おき、かしこ。」(文久3年5月17日)
「おとめさまへ 此手がみ人にハ けしてけして見せられんぞよ、かしこ。」(元治元年6月28日)
(宮地佐一郎『龍馬の手紙』講談社学術文庫)
※引用に際して、繰り返しを表す記号は一般的な表記に改めた。以降も同様。
坂本竜馬が姉乙女に送った手紙のいくつかには、このような一文が添えられています。龍馬は筆まめで、現存しているだけでも140通近くあるといいます。
28歳で脱藩した龍馬は、現在進行中の重大な出来事や自分の置かれている立場、苦悩や喜びといった真情などを、包み隠さず乙女に書き送っているので、「この手紙の中身のことは、人に言ってはいけませんよ。お独りの胸に留めておいてくださいね」「だれにも見せてはいけませんよ」と、釘を刺しているのです。
姉に対して強気でそう言ってはいるものの、土佐弁が興を添えているからなのでしょうか、やんちゃな甘えん坊ぶりを垣間見るようで何ともかわいらしい気がします。
5人兄弟の末っ子で、10歳で母を亡くした龍馬を母代わりに養育し、武芸や学問を教えたのがすぐ上の姉、乙女でした。彼女は、175センチほどの長身で体格がよく、男顔負けの文武両道の人だったといいます。
脱藩亡命後の龍馬は、不穏極まる世の中で、明日をも知れぬ身でありながら、「日本を洗濯すること」、「世界の海援隊を創ること」を目指して東奔西走します。そして、その合間を縫って、自分の考えや行動が間違っていないことを、乙女に知っておいてもらいたい一心でせっせと手紙を書き送っていたのです。
その中でも有名な「日本を今一度せんたくいたし」の決心が書かれている、文久3年6月29日付けの一通を紹介したいと思います。かなり長文なので、途中省略しています。
この文ハ極大事の事斗ニて、け(=決)してべちやべちやシャベクリ(=饒舌)にハ、ホヽヲホヽヲいややの、けして見せられるぞへ
(中略)
然ニ誠になげくべき事ハながと(=長門)の国に軍初り、後月より六度の戦に甚利すくなく、あきれはてたる事ハ、其長州でたゝかいたる船を江戸でしふく(=修復)いたし 又長州でたゝかい申候。
皆姦吏の夷人と内通いたし候ものニて候。 右の姦吏などハよほど勢もこれあり、大勢ニて候へども、龍馬二三家の大名とやくそく(=約束)をかたくし、同志をつのり、朝廷より先ヅ神州をたもつの大本をたて、夫より江戸の同志はたもと大名其余段々と心を合セ、右申所の姦吏を一事に軍いたし打殺、 日 本 を今一度せんたく(=洗濯)いたし申候事ニいたすべくとの神 願ニて候。此思付を大藩にもすこむ(=頗)る同意して、使者を 内々 下サルヽ事両度。然ニ龍馬すこしもつかへをもとめず。実に天下に人ぶつのなき事これを以てしるべく、なげくべし。
(中略)
然ニ土佐のいもほり(=芋掘)ともなんともいわれぬ、いそふろ(=居候)に 生て、一人の力で天下うごかすべきハ、是又天よりする事なり。かふ申てもけしてけしてつけあがりハせず、(略)御安心なされかし。
穴かしこや。
弟 直陰
(同上)
※かたかなルビは龍馬の手紙のママ
※その他のルビ、および“(= )”は引用者による
「夷人と内通」したというのは、外国軍艦が下関で長州を砲撃したとき、幕府は異人と内通して壊れた船を横浜で修復し、そしてまた、長州と戦ったということで、幕府が異人の手を借りて長州を打ったことに龍馬は憤慨し、「日本を今一度せんたく」しなければならないと、決意するのです。
また、天下に人物のいないことを嘆いていますが、それならば自分一人の力で天下を動かすしかないと吐露しているところは、さすが孤高の人というほかありません。
直陰は、龍馬の諱です。
また、冒頭の「べちゃべちゃシャベクリにハ、ホヽヲホヽヲいややの・・・」というのは、方言を交えた擬声語らしいのですが、これから話す「極大事の事」とはずいぶんかけ離れた、ユーモラスなあいさつ文ですね。重大な打ち明け話を聞く前に、ちょっと気持ちをほぐしてくださいという、龍馬らしい気配りが伝わってきてほほえましい限りです。
坂本龍馬 天保6(1835)年 11月15日 土佐にて生誕
慶應3(1867)年 11月15日 京都 近江屋にて暗殺
清し女
(肖像写真は国立国会図書館蔵)